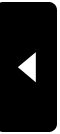2021年08月22日
ローカル七十二候 第37~45候(立秋・処暑・白露)
二十四節気「立秋(りっしゅう)」
第37候 涼風至(すづかぜ いたる) 8月7日~
「夏休みのこども行事 鮎つかみ、炭火焼、花火」」
花背校区・広河原で里山フェスティバル。子どもが川でつかんだ鮎を、地元・鞍馬炭で焼いて食す。葛川への道中、久多で葛川PTAのデーキャンプに遭遇。コロナ禍の親子の笑顔、有難く心にしみる。
第38候 寒蝉鳴(ひぐらし なく) 8月12日~
「帰省なしのお盆 長雨で通行止、滋賀のまちで過ごす」
去年に続き、コロナで帰省できず。今年就職した次男以外の家族が守山の家に集合。夫が葛川に帰った後、長雨で花背へ行く道が全て通行止となり、思いがけず、まちに3泊。買い物の人混みにおののく。
「オオハンゴンソウ 花が落ち始める」
あちこちで黄色いお花畑となっていたオオハンゴンソウの花が散り始めた。花が落ちると、途端にどこに生えているかわからなくなる。実をつける前に撤去せねば。
第39候 蒙霧升降(ふかききり まとう) 8月18日~
「長雨の晴れ間 園庭で久々の外遊び・水遊び」
8月に入り、雨続きで、園児たちと外に出かける機会がほとんど作れず。雨のない朝、今日こそはと、園庭へ。お日様も顔を出し、プールも出して水遊び。ずぶ濡れになったところで雨が降り始める。
二十四節気「処暑(しょしょ)」
第40候 綿柎開(わたのはなしべ ひらく) 8月23日~
「夏の最後の?!川遊び お出かけ先で咲き誇る葛の花」
この夏、貴重な一日晴れの日。お弁当給食を持って、花脊・別所へお出かけ。暑さにまずは水着で渓流へ。岸の草の中に小魚の群れ。反対岸の崖にはあちこちの赤紫の小花の束に目を奪われる。

「園庭の綿、花咲かず」
「綿柎開(わたのはなしべ ひらく)」の第40候。
4、5月、園庭のプランターに植えた綿の種は芽が出ず。6月に琵琶博で苗を分けてもらって植えるも、高さ3,40センチまでは育ったが、花は咲かず、実はなりそうにない。
第41候 天地始粛(てんち はじめて さむし) 8月28日~
「赤とんぼの群れ ススキの穂 うろこ雲」
夏の名残、晴天が続く。ようやく園で今年つけた梅を干す。朝、出勤しようと玄関を出ると、トンボが群れ、ススキの穂だらけなのに気づく。園児らと川遊びの空にうろこ雲。

第42候 禾乃登(こくもの すなわち みのる) 9月2日~
「今年最後の川遊び 魚・虫を追いまくる」
9月に入り晴れの日に川へお出かけ。ライフジャケットを着て、深みに浮かび、魚を狙う。冷えた身体を園児らとアスファルトに寝転んで温める。トンボ蝶バッタを追いかけ網をふる子らの姿を見守る。
二十四節気「白露(はくろ)」
第43候 草露白(くさのつゆ しろし) 9月7日~
「早朝冷え込み、こたつを出す」
ここ2,3日、晴れたが早朝冷え込む。曇天の日の朝、長女の求めに応じて、こたつをセット。末娘も入れて女三人で入って朝食。じんわりと身体が温もりゆるむのを感じる。白露を過ぎ、秋分へ向かう日。
第44候 鶺鴒鳴(せきれい なく) 9月12日~
「散歩中、学校近くに真っ赤な彼岸花」
秋の遠足の練習に大布施トンネルまで長めのお散歩へ出発。学校への大階段を下りたところで今年初めて彼岸花を花背で見つける。
第45候 玄鳥去(つばめ さる) 9月18日~
「隣家・園庭、あちこちでキンモクセイ香る」
今年は、匂いより先に花が咲いているのに気づいた。その2,3日後にあの香りに深呼吸する。園庭の熊の電柵にかかった枝葉を大胆に切った樹木がキンモクセイだったことを香りで知る。
第37候 涼風至(すづかぜ いたる) 8月7日~
「夏休みのこども行事 鮎つかみ、炭火焼、花火」」
花背校区・広河原で里山フェスティバル。子どもが川でつかんだ鮎を、地元・鞍馬炭で焼いて食す。葛川への道中、久多で葛川PTAのデーキャンプに遭遇。コロナ禍の親子の笑顔、有難く心にしみる。
第38候 寒蝉鳴(ひぐらし なく) 8月12日~
「帰省なしのお盆 長雨で通行止、滋賀のまちで過ごす」
去年に続き、コロナで帰省できず。今年就職した次男以外の家族が守山の家に集合。夫が葛川に帰った後、長雨で花背へ行く道が全て通行止となり、思いがけず、まちに3泊。買い物の人混みにおののく。
「オオハンゴンソウ 花が落ち始める」
あちこちで黄色いお花畑となっていたオオハンゴンソウの花が散り始めた。花が落ちると、途端にどこに生えているかわからなくなる。実をつける前に撤去せねば。
第39候 蒙霧升降(ふかききり まとう) 8月18日~
「長雨の晴れ間 園庭で久々の外遊び・水遊び」
8月に入り、雨続きで、園児たちと外に出かける機会がほとんど作れず。雨のない朝、今日こそはと、園庭へ。お日様も顔を出し、プールも出して水遊び。ずぶ濡れになったところで雨が降り始める。
二十四節気「処暑(しょしょ)」
第40候 綿柎開(わたのはなしべ ひらく) 8月23日~
「夏の最後の?!川遊び お出かけ先で咲き誇る葛の花」
この夏、貴重な一日晴れの日。お弁当給食を持って、花脊・別所へお出かけ。暑さにまずは水着で渓流へ。岸の草の中に小魚の群れ。反対岸の崖にはあちこちの赤紫の小花の束に目を奪われる。

「園庭の綿、花咲かず」
「綿柎開(わたのはなしべ ひらく)」の第40候。
4、5月、園庭のプランターに植えた綿の種は芽が出ず。6月に琵琶博で苗を分けてもらって植えるも、高さ3,40センチまでは育ったが、花は咲かず、実はなりそうにない。
第41候 天地始粛(てんち はじめて さむし) 8月28日~
「赤とんぼの群れ ススキの穂 うろこ雲」
夏の名残、晴天が続く。ようやく園で今年つけた梅を干す。朝、出勤しようと玄関を出ると、トンボが群れ、ススキの穂だらけなのに気づく。園児らと川遊びの空にうろこ雲。

第42候 禾乃登(こくもの すなわち みのる) 9月2日~
「今年最後の川遊び 魚・虫を追いまくる」
9月に入り晴れの日に川へお出かけ。ライフジャケットを着て、深みに浮かび、魚を狙う。冷えた身体を園児らとアスファルトに寝転んで温める。トンボ蝶バッタを追いかけ網をふる子らの姿を見守る。
二十四節気「白露(はくろ)」
第43候 草露白(くさのつゆ しろし) 9月7日~
「早朝冷え込み、こたつを出す」
ここ2,3日、晴れたが早朝冷え込む。曇天の日の朝、長女の求めに応じて、こたつをセット。末娘も入れて女三人で入って朝食。じんわりと身体が温もりゆるむのを感じる。白露を過ぎ、秋分へ向かう日。
第44候 鶺鴒鳴(せきれい なく) 9月12日~
「散歩中、学校近くに真っ赤な彼岸花」
秋の遠足の練習に大布施トンネルまで長めのお散歩へ出発。学校への大階段を下りたところで今年初めて彼岸花を花背で見つける。
第45候 玄鳥去(つばめ さる) 9月18日~
「隣家・園庭、あちこちでキンモクセイ香る」
今年は、匂いより先に花が咲いているのに気づいた。その2,3日後にあの香りに深呼吸する。園庭の熊の電柵にかかった枝葉を大胆に切った樹木がキンモクセイだったことを香りで知る。
2021年07月04日
ローカル七十二候 第28~36候(夏至・小暑・大暑)
二十四節気「夏至(げし)」
第28候 乃東枯(なつかれくさ かるる) 6月21日~
「家の前のクリの木の花、満開」
昨秋、花背に引っ越してまもなく、たくさんの実を採らせてもらったクリの木。花がたくさん咲いた。秋がくるのが楽しみ。

第29候 菖蒲華(あやめ はなさく) 6月26日~
「夜、家の前の川で、末娘と蛍の光を追う」
少し前からあちこちで蛍出没の話を聞いていたが、ようやく夜、家の前に出ることができた。橋の上から川上を見通すと、両岸から川を渡る光。末娘が指差し声をあげて喜ぶ様子が心にしみる。
第30候 半夏生(はんげ しょうず) 7月2日~
「園庭の畑で、キュウリ初収穫」
園児らと苗を植えたキュウリ。黄色い花が咲き、小さな実がなり、大きくなった。年長組の二人に収穫してもらう。トゲトゲに触れ、青臭い匂いをかぎ、画用紙いっぱいに描く。
「ご近所の梅の実採り、園児らと梅仕事」
ご近所の梅の実採り二回目。8キロの梅を園児らと洗い、拭き、青梅と黄梅と分けて、へそとりして、黄梅は塩で漬け梅干しに。青梅は冷凍して砂糖に漬けて梅ジュースに。木にはまだまだ実が残る。
「半夏生 コロナで虫送りは中止」
例年この時季に、お向かいのお家の庭にハンゲショウが咲き、地元では「虫送り」行事を行う。わが家のある集落では今年は中止とのこと。(お隣の久多では、行われた。)

二十四節気「小暑(しょうしょ)」
第31候 温風至(あつかぜ いたる) 7月7日~
「七夕会 願い事を笹に飾り、七夕メニュー」
五色の短冊に、園児一人ひとりから願い事を聞いて書き、じいじが用意してくれた笹に自分でつけた笹飾り。旧暦の七夕(8/14)までは無理でも、次の上弦(7/17)までは飾っておきたい。
「雨ふり散歩 水たまりでジャブジャブ」
梅雨の長雨、久しぶりのお散歩。雨の降る中、カッパ着て出発。水たまりに長靴で入る。だんだん水しぶきが楽しくなって足踏み。寝っ転がる子も。私も負けじとジャブジャブ。ずぶ濡れに光る笑顔。
第32候 蓮始開(はす はじめて ひらく) 7月12日~
「久多・北山友禅菊がちらほら咲き」
昨夏、葛川から花背への通勤途中に心を満たしてくれた久多の北山友禅菊が、ちらほら咲いてきた。今年は通りがかりに苗植えもお手伝い。満開になるのが楽しみ。
第33候 鷹乃学習(たか すなわち わざをなす) 7月17日~
「梅雨明け オオハンゴンソウの花、満開」
歩いているとき見つけるたびに駆除してたオオハンゴンソウ。花が咲き始めたかと思ったら、通勤途中、あちこちに黄色い花の大群落。去年はきれいなお花畑だと思ってたけれど。種が飛んで広がりませんように。
「夏の貫けるような青空の下、水着で園児らと川下り」
夏の川遊びの手始めに、梅雨前、生き物探しした林道の渓流を下る。大きな土管を歩きぬけ、苔で滑る石に、慎重に足を運ぶ。流れの冷たさに歓声をあげ、冷えた身体を道路とお茶で温める。
二十四節気「大暑(たいしょ)」
第34候 桐始結花(きり はじめて はなをむすぶ) 7月22日~
「久多・北山友禅菊が満開」
平日の早朝、急用で、葛川にいる夫と久多で待ち合わせ。道沿いの北山友禅菊が満開で、カメラを持った見物客が幾組も。用事を終え、二人で、束の間の友禅菊ドライブ。薄紫が心にしみる。

「園庭で育てた藍の葉を摘み叩き染め」
藍が立派に育った。園児たちに好きな葉を2,3枚摘み取り、園庭に広げた白い大きな布の上に好きに並べ、その上を金づちでコンコン丁寧に叩いてもらう。葉の形に汁がついた布は、洗うと水色に染まる。

葉っぱのスタンピングも添えて
第35候 土潤溽暑(つち うるおうて むしあつし) 7月28日~
「夏休み・小中学生が保育園で伝統の流しそうめん」
こどもクラブ参加の小中学生が保育園で流しそうめんを頂く。最後は「濡れる」のがお約束の行事。食後、園長せんせとホースの水かけ合戦。園庭で園児に戻ったような無邪気な顔が心に残る。
第36候 大雨時行(たいう ときどきに ふる) 8月2日~
「夏休み・小中学生が園児たちと本気の川遊び」
こどもクラブ参加の小中学生が近くの川へ。ライジャケ着て、川流れ、岩から飛び降り潜ったり。園児たちと小魚採り。給食後、希望で全員お昼寝。その後は本気で宿題やっつけタイム。素敵な夏休み!
第28候 乃東枯(なつかれくさ かるる) 6月21日~
「家の前のクリの木の花、満開」
昨秋、花背に引っ越してまもなく、たくさんの実を採らせてもらったクリの木。花がたくさん咲いた。秋がくるのが楽しみ。

第29候 菖蒲華(あやめ はなさく) 6月26日~
「夜、家の前の川で、末娘と蛍の光を追う」
少し前からあちこちで蛍出没の話を聞いていたが、ようやく夜、家の前に出ることができた。橋の上から川上を見通すと、両岸から川を渡る光。末娘が指差し声をあげて喜ぶ様子が心にしみる。
第30候 半夏生(はんげ しょうず) 7月2日~
「園庭の畑で、キュウリ初収穫」
園児らと苗を植えたキュウリ。黄色い花が咲き、小さな実がなり、大きくなった。年長組の二人に収穫してもらう。トゲトゲに触れ、青臭い匂いをかぎ、画用紙いっぱいに描く。
「ご近所の梅の実採り、園児らと梅仕事」
ご近所の梅の実採り二回目。8キロの梅を園児らと洗い、拭き、青梅と黄梅と分けて、へそとりして、黄梅は塩で漬け梅干しに。青梅は冷凍して砂糖に漬けて梅ジュースに。木にはまだまだ実が残る。
「半夏生 コロナで虫送りは中止」
例年この時季に、お向かいのお家の庭にハンゲショウが咲き、地元では「虫送り」行事を行う。わが家のある集落では今年は中止とのこと。(お隣の久多では、行われた。)
二十四節気「小暑(しょうしょ)」
第31候 温風至(あつかぜ いたる) 7月7日~
「七夕会 願い事を笹に飾り、七夕メニュー」
五色の短冊に、園児一人ひとりから願い事を聞いて書き、じいじが用意してくれた笹に自分でつけた笹飾り。旧暦の七夕(8/14)までは無理でも、次の上弦(7/17)までは飾っておきたい。
「雨ふり散歩 水たまりでジャブジャブ」
梅雨の長雨、久しぶりのお散歩。雨の降る中、カッパ着て出発。水たまりに長靴で入る。だんだん水しぶきが楽しくなって足踏み。寝っ転がる子も。私も負けじとジャブジャブ。ずぶ濡れに光る笑顔。
第32候 蓮始開(はす はじめて ひらく) 7月12日~
「久多・北山友禅菊がちらほら咲き」
昨夏、葛川から花背への通勤途中に心を満たしてくれた久多の北山友禅菊が、ちらほら咲いてきた。今年は通りがかりに苗植えもお手伝い。満開になるのが楽しみ。
第33候 鷹乃学習(たか すなわち わざをなす) 7月17日~
「梅雨明け オオハンゴンソウの花、満開」
歩いているとき見つけるたびに駆除してたオオハンゴンソウ。花が咲き始めたかと思ったら、通勤途中、あちこちに黄色い花の大群落。去年はきれいなお花畑だと思ってたけれど。種が飛んで広がりませんように。
「夏の貫けるような青空の下、水着で園児らと川下り」
夏の川遊びの手始めに、梅雨前、生き物探しした林道の渓流を下る。大きな土管を歩きぬけ、苔で滑る石に、慎重に足を運ぶ。流れの冷たさに歓声をあげ、冷えた身体を道路とお茶で温める。
二十四節気「大暑(たいしょ)」
第34候 桐始結花(きり はじめて はなをむすぶ) 7月22日~
「久多・北山友禅菊が満開」
平日の早朝、急用で、葛川にいる夫と久多で待ち合わせ。道沿いの北山友禅菊が満開で、カメラを持った見物客が幾組も。用事を終え、二人で、束の間の友禅菊ドライブ。薄紫が心にしみる。

「園庭で育てた藍の葉を摘み叩き染め」
藍が立派に育った。園児たちに好きな葉を2,3枚摘み取り、園庭に広げた白い大きな布の上に好きに並べ、その上を金づちでコンコン丁寧に叩いてもらう。葉の形に汁がついた布は、洗うと水色に染まる。

葉っぱのスタンピングも添えて
第35候 土潤溽暑(つち うるおうて むしあつし) 7月28日~
「夏休み・小中学生が保育園で伝統の流しそうめん」
こどもクラブ参加の小中学生が保育園で流しそうめんを頂く。最後は「濡れる」のがお約束の行事。食後、園長せんせとホースの水かけ合戦。園庭で園児に戻ったような無邪気な顔が心に残る。
第36候 大雨時行(たいう ときどきに ふる) 8月2日~
「夏休み・小中学生が園児たちと本気の川遊び」
こどもクラブ参加の小中学生が近くの川へ。ライジャケ着て、川流れ、岩から飛び降り潜ったり。園児たちと小魚採り。給食後、希望で全員お昼寝。その後は本気で宿題やっつけタイム。素敵な夏休み!
2021年05月20日
ローカル七十二候 第19~27候(立夏・小満・芒種)
二十四節気「立夏(りっか)」
第19候 蛙始鳴(かわず はじめて なく) 5月5日~
「おつきようか、身近な自然の彩りを供える」
花背での伝統行事・卯月八日。近年復活された地元の方に教わる。十字に組んだ竹に身近な季節の樹花を飾り、草餅をお供え。ヤマツツジ、卯の花(ウツギ)、フジ、モミジの青葉など。

「早朝、キツツキの音・幾種もの蛙・鳥の声に暫し聴き入る」
朝5時、布団の中で外の明るさを感じつつまどろんでいると、キツツキの音。耳を傾けるとたくさんの生き物の声が飛び込み心を奪われる。
第20候 蚯蚓出(みみず いずる) 5月10日~
「園庭の畑にきゅうり・ミニトマト・ひょうたんの苗植え」
保育所のじいじが整えた畝に、子どもたちがお手々ショベルで穴を掘り、苗を植え、ぞうさんジョウロで水やり。プランターの土を返したら、1ミリ程の極小カタツムリ、セミの幼虫にも出会う。
第21候 竹笋生(たけのこ しょうず) 5月16日~
「園庭の梅の実落ちる」
ここ、花背で、いち早く春を告げてくれた保育園の梅。雨の合間のお散歩に出ようとしたら、足元にたくさんの小さな青い梅の実。子どもたちが拾い始め、みんなで丁寧に集めて、竹籠に入れる。
「卵から孵ったカマキリ・オタマジャクシお絵描き」
地元の方が届けてくれたり、お散歩のときに見つけて持ち帰った卵たちが次々と孵る。毎日少しずつ大きくなり、雨の日に、園児らと生き物観察し、絵を描いて、自然に返す。

二十四節気「小満(しょうまん)」
第22候 蚕起食桑(かいこ おきて くわを はむ) 5月17日~
「名残のフジの花を摘み、天ぷらで頂く」
園児らとオタマジャクシの水と餌をとりに林道散歩。タニウツギのピンクの花が満開。終わりのフジの花房も取り、園に戻りボールにしごく。小さな花の山の匂いを一人ずつかいで、念願の天ぷらを味わう。

「園児・ばあちゃんと朴の若葉を集める」
朴葉とりに山へ。枝にロープをかけて引っ張り、放射状に大きく広がる葉々の輪をばあちゃんが摘み取る。皆で傷つかぬよう持ち帰り、一枚ずつ葉をばらす。香しい花とつぼみも、鉢に活けて玄関に飾る。


こどもたちのごはんづくり。年中組で朴葉ずし、年長組でお味噌汁を作りました!
第23候 紅花栄(べにばな さかう) 5月26日~
「園児らと摘んだ茶葉で烏龍茶づくり」
園のご近所さんの茶葉がまさに摘み時。かつてお母様がお茶を作っていたそう。みんなで一芯二葉を摘ませて頂く。天日に当て、ザルで揺らし、手もみ火入れを重ねて烏龍茶に仕上げ、茶葉の主にも届ける。

「初夏の田畑に遠足し生き物と憩う」
梅雨の晴れ間、おにぎりとおかずを自分でつめたお弁当をリュックに入れ、田畑にお出かけ。蝶、虫、貝、蛙、魚、鳥、たくさんの生き物。シロツメグサで作った結婚指輪、園児が大人にプレゼント。
第24候 麦秋至(むぎのとき いたる) 5月31日~
「卵から、ついにカエルになる」
4月下旬、林道散歩のとき持ち帰ったゼリーのロープ。卵からオタマジャクシがかえり、前脚、後ろ脚が生え、ついにしっぽがなくなったカエルが石の上に。ガマガエルの子。自然の中にみんな返してあげました。

「玄関先でアカショウビンが鳴く」
朝、あの独特のアカショウビンの声を聞き始める。声が近いので外に出てみると、玄関先のすぐ先で声がする。目をこらすが、葛川で一度だけ目にしたことがあるあの赤い姿は見ることはできなかった。
二十四節気「芒種(ぼうしゅ)」
第25候 螳螂生(かまきり しょうず) 6月5日~
「園児らと蛙の駅でモリアオガエルと戯れる」
花背のそば、京北・灰屋の蛙の駅にお出かけ。樹上に鈴なりのモリアオガエルの卵、水中には夥しい数のオタマジャクシ、緑鮮やかな蛙の姿もあちこちに。川で水遊び。けろったさんからお土産も頂きました。

第26候 腐草為蛍(くされたるくさ ほたると なる) 6月11日~
「ドクダミ・山椒・梅しごと」
園庭のドクダミを抜いて干してお茶に。お花も摘んでチンキに。山椒の実を外し、梅のへそを取る。
そういえば、園庭にアリの大移動行列も。ほんの数十分のできごと、子どもたちと観察できた。
「ご近所さんちで木苺、神社近くで桑の実」
園児たちとお散歩で、季節のなりものに舌鼓を打つ。小さな指で小さな実をつまんで口へ、つまんで口へ。雨がなくても傘は必携。(曲がった柄で枝先を引っかけて取る!)

「蕗摘みの時季、熊が出た!」
お散歩から帰ると、クマ出没の情報。園のばあちゃん曰く、蕗摘みのこの時季に出る、のだそうだ。登下校に歩く心臓破りの階段も、園庭の周りも、電柵を通電。週末まで、園児の送迎車は玄関前へ。
第27候 梅子黄(うめのみ きばむ) 6月16日~
「キイチゴ・グミ・ハグロトンボに夢中」
お弁当給食を持ってお出かけ。道沿いの木苺を採って口にしながら歩き、庭先にたわわになったグミの実を集め、草原でハグロトンボや小さなバッタ採りに熱中。小川では水遊びも。グミは氷砂糖で漬ける。

「小中学生が花脊の笹でちまきを作り完売!」
地元の小中学生の有志がやってるちまきプロジェクト。旧暦の端午の節句にと、地元のチマキザサを分けて頂いて、ちまきを230本作って販売。「香り高きちまき」でした。
https://instagram.com/teamtell_hanase/
第19候 蛙始鳴(かわず はじめて なく) 5月5日~
「おつきようか、身近な自然の彩りを供える」
花背での伝統行事・卯月八日。近年復活された地元の方に教わる。十字に組んだ竹に身近な季節の樹花を飾り、草餅をお供え。ヤマツツジ、卯の花(ウツギ)、フジ、モミジの青葉など。

「早朝、キツツキの音・幾種もの蛙・鳥の声に暫し聴き入る」
朝5時、布団の中で外の明るさを感じつつまどろんでいると、キツツキの音。耳を傾けるとたくさんの生き物の声が飛び込み心を奪われる。
第20候 蚯蚓出(みみず いずる) 5月10日~
「園庭の畑にきゅうり・ミニトマト・ひょうたんの苗植え」
保育所のじいじが整えた畝に、子どもたちがお手々ショベルで穴を掘り、苗を植え、ぞうさんジョウロで水やり。プランターの土を返したら、1ミリ程の極小カタツムリ、セミの幼虫にも出会う。
第21候 竹笋生(たけのこ しょうず) 5月16日~
「園庭の梅の実落ちる」
ここ、花背で、いち早く春を告げてくれた保育園の梅。雨の合間のお散歩に出ようとしたら、足元にたくさんの小さな青い梅の実。子どもたちが拾い始め、みんなで丁寧に集めて、竹籠に入れる。
「卵から孵ったカマキリ・オタマジャクシお絵描き」
地元の方が届けてくれたり、お散歩のときに見つけて持ち帰った卵たちが次々と孵る。毎日少しずつ大きくなり、雨の日に、園児らと生き物観察し、絵を描いて、自然に返す。

二十四節気「小満(しょうまん)」
第22候 蚕起食桑(かいこ おきて くわを はむ) 5月17日~
「名残のフジの花を摘み、天ぷらで頂く」
園児らとオタマジャクシの水と餌をとりに林道散歩。タニウツギのピンクの花が満開。終わりのフジの花房も取り、園に戻りボールにしごく。小さな花の山の匂いを一人ずつかいで、念願の天ぷらを味わう。

「園児・ばあちゃんと朴の若葉を集める」
朴葉とりに山へ。枝にロープをかけて引っ張り、放射状に大きく広がる葉々の輪をばあちゃんが摘み取る。皆で傷つかぬよう持ち帰り、一枚ずつ葉をばらす。香しい花とつぼみも、鉢に活けて玄関に飾る。


こどもたちのごはんづくり。年中組で朴葉ずし、年長組でお味噌汁を作りました!
第23候 紅花栄(べにばな さかう) 5月26日~
「園児らと摘んだ茶葉で烏龍茶づくり」
園のご近所さんの茶葉がまさに摘み時。かつてお母様がお茶を作っていたそう。みんなで一芯二葉を摘ませて頂く。天日に当て、ザルで揺らし、手もみ火入れを重ねて烏龍茶に仕上げ、茶葉の主にも届ける。
「初夏の田畑に遠足し生き物と憩う」
梅雨の晴れ間、おにぎりとおかずを自分でつめたお弁当をリュックに入れ、田畑にお出かけ。蝶、虫、貝、蛙、魚、鳥、たくさんの生き物。シロツメグサで作った結婚指輪、園児が大人にプレゼント。
第24候 麦秋至(むぎのとき いたる) 5月31日~
「卵から、ついにカエルになる」
4月下旬、林道散歩のとき持ち帰ったゼリーのロープ。卵からオタマジャクシがかえり、前脚、後ろ脚が生え、ついにしっぽがなくなったカエルが石の上に。ガマガエルの子。自然の中にみんな返してあげました。

「玄関先でアカショウビンが鳴く」
朝、あの独特のアカショウビンの声を聞き始める。声が近いので外に出てみると、玄関先のすぐ先で声がする。目をこらすが、葛川で一度だけ目にしたことがあるあの赤い姿は見ることはできなかった。
二十四節気「芒種(ぼうしゅ)」
第25候 螳螂生(かまきり しょうず) 6月5日~
「園児らと蛙の駅でモリアオガエルと戯れる」
花背のそば、京北・灰屋の蛙の駅にお出かけ。樹上に鈴なりのモリアオガエルの卵、水中には夥しい数のオタマジャクシ、緑鮮やかな蛙の姿もあちこちに。川で水遊び。けろったさんからお土産も頂きました。

第26候 腐草為蛍(くされたるくさ ほたると なる) 6月11日~
「ドクダミ・山椒・梅しごと」
園庭のドクダミを抜いて干してお茶に。お花も摘んでチンキに。山椒の実を外し、梅のへそを取る。
そういえば、園庭にアリの大移動行列も。ほんの数十分のできごと、子どもたちと観察できた。
「ご近所さんちで木苺、神社近くで桑の実」
園児たちとお散歩で、季節のなりものに舌鼓を打つ。小さな指で小さな実をつまんで口へ、つまんで口へ。雨がなくても傘は必携。(曲がった柄で枝先を引っかけて取る!)

「蕗摘みの時季、熊が出た!」
お散歩から帰ると、クマ出没の情報。園のばあちゃん曰く、蕗摘みのこの時季に出る、のだそうだ。登下校に歩く心臓破りの階段も、園庭の周りも、電柵を通電。週末まで、園児の送迎車は玄関前へ。
第27候 梅子黄(うめのみ きばむ) 6月16日~
「キイチゴ・グミ・ハグロトンボに夢中」
お弁当給食を持ってお出かけ。道沿いの木苺を採って口にしながら歩き、庭先にたわわになったグミの実を集め、草原でハグロトンボや小さなバッタ採りに熱中。小川では水遊びも。グミは氷砂糖で漬ける。

「小中学生が花脊の笹でちまきを作り完売!」
地元の小中学生の有志がやってるちまきプロジェクト。旧暦の端午の節句にと、地元のチマキザサを分けて頂いて、ちまきを230本作って販売。「香り高きちまき」でした。
https://instagram.com/teamtell_hanase/