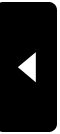2024年01月03日
後輩の追悼の会(追加改題) 2006年11月01日17:17
先週の土曜、大学時代のサイクリング部の一年下の後輩の追悼の会があった。
この日には、近江上布の原型となる高宮布を実際に手にとって見れる講演会があったり、スピ仲間が京都のおっちゃん訪問をしたりと、重要なイベントが重なっていた。しかし、連れ合いと子どもを残して、朝早く、名古屋へ向かった。
公立美術館で学芸員をしていた後輩。
追悼の会は美術館の上司とサイクリング部OB有志で企画運営。出席者は当初の予想を遥かに超えて100名余り。そのうち、サイクリング部関係は30名。大学研究室関係、美術館関係、工芸、現代美術の作家などなどが集まる。会場のBGMは後輩コレクションのCDから選曲。事前に送られた計画を見て、この文化レベルの高さについていけるだろうかと少し不安だった。
会場準備のために早めに集まった後輩数名と会場で合流。
あいさつもそこそこに、会場までの道案内係や受付係をきめる。
そうしていると、後輩のご両親が到着。お母さまにはご実家でお会いしたことがある。ごあいさつに行くと「あれから荷物を整理していましたら、サイクリング部の合宿委員の通帳も出てきたんですよ。」とのこと。
そうだ、彼女は合宿委員だったと思い出す。
お父さまとははじめてお会いした。成人式のお祝いに父子2人でヨーロッパ旅行し、昨年末も2人で旅行するほど仲がよかったようだ。ごあいさつすると「大学では周りの人がすごい人ばかりだとよく言ってました。」と返された。そのときはピンとこなかったが、お父さまは娘を京都に出したことをとても後悔されておられたのだった。
---
そうしているうちに、出席者は次々と集まってくる。
私は会場のある階のエレベーターの前でお出迎えしながら、出席者を受付へと誘導。懐かしい顔に思わず何ともいえない親しさがこみあげてくる。
時間にはほとんど出席者がそろい、時間通りに会が始まる。
追悼の場で、見知らぬ者が集っていることもあり、初めは空気が固かった。美術館の上司のはじめの言葉、大学研究室の指導教官、仲間からの言葉、サイクリング部時代の写真上映、仲間からの言葉・・・と進むにつれ場は和み、献杯、会食で一気に交流が始まる。
学生時代の彼女はいつも笑顔で誰にでも親切で、クラブの同輩のOちゃんが語ったように「○○さんはえらいよね~。私もがんばらなくちゃ」といつも謙虚で志が高かった。
研究室では、美学美術の世界ではマイナーな「工藝」の分野に真摯に取り組み、見事に光を当てる研究成果をあげて、彼女は活躍の場を大学から美術館に移した。
クラブの女子部員数名が集っていたところへ、お父さまがごあいさつされた。ここでも再び、後輩がいつも周りの人がすごいと言っていたことに触れ「こんなことを言ってはよくないが、親としては、バカな子でいいから生きていてほしかった」と声をつまらせながら語られた。みんな慰めの言葉をかけようとしたが、私には何も言えなかった。
彼女の訃報に触れて4ヶ月あまり。私はどうやったら乗り越えられるか、試行錯誤した。クラブの集まりの機会を作ったり、メッセージを集めてご実家に送ったり、美術館やご実家を訪問したり、追悼の会の準備に携わったり・・・。その中で、彼女の死をかなり昇華できた気がしていた。
しかし、ご両親はまだまだ娘の死を抱えて生きている。
最後のお父さまの言葉に「娘が亡くなって147日。どうしたらよかったのかと後悔しない日はない」とも。
クラブの同輩たちを見ても整理できてない様子が見える者もいた。後輩の死の重さを改めて感じる。
・・・再び、写真の上映が始まる。
今度は美術館に入ってからの写真である。作家を訪れたり、美術館の展示準備をしたり、イベントのお茶会での着物姿など。
続いて、関わりのあった作家からの言葉。彼女の的確な眼と才能を、周りに支えられながら発揮してきたことが語られる。
後輩は美術館に入り、現代美術にも取り組む。工藝と現代美術、一見すると対極にあるこれらの世界を両方パラレルに的確に見ることができる類稀な逸材であった。
ある作家は”生きているのも辛い状態であるのは分かるけど、それでも生きて彼女の才能を発揮して仕事を残してほしかった”と語った。
後輩の病と才能は切り離すことができないものだったのかもしれない、とふと思いがよぎる。
後輩がお気に入りで通いつめたギャルソンの店員の言葉もあった。後輩の見る眼、語る言葉にとても励まされたとのこと。その様子に、学生時代の彼女が重なった。
後輩は、この世に出る前の才能を見抜き、光を当て、世に出す仕事も数多く行っていた。その中の一人で今はメキシコで活躍する作家のmixiの日記を読んで、後輩は孤独な中で旅立ったのではないと救われた気持ちになったのを思い出す。
会場には、その作家が作ったTシャツを着て出席された方もいらっしゃったことを帰ってきてから知り、追悼の会の場でクラブ関係以外の方々とほとんど交流してなかったことを少し悔いた。
最後に、お父さまの言葉、サイクリング部同輩のAくんの言葉があって、追悼の会は終了した。
お父さまが”年末に娘と旅行したあと、今度は家族みんなで行こうと話していた。娘はいないが、ぜひみんなで行きたい”と語られていたのが、わずかな救いだった。
片づけをして、美術館の上司にあいさつし固い握手を交わして会場をあとにした。
-----
このあと、サイクリング部員の集いがあったが、私は参加せず家路についた。
ぐったりと心身の疲れをひきずりながらたどり着いた我が家の食卓で私を出迎えていたのは、とても食べようとして切ったとは思えない、へたがいくつかに切り取られた不思議な様相のカキだった。
こうして、長い一日が終わった。
次の日記へつづく?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
コメント ようちゃん2006年11月01日 19:33
太陽のウエイブスペルって25日(水)からでした。なぜか土曜が初日だと勘違いしていましたので、日記を一部削除しました。
不思議な様相のカキの秘密は、息子2の伝説として、翌朝、連れ合いから語られたのでした。つづく
おね2006年11月02日 07:09
死は決して失われることのない事実ではあるけれども、
それをどういう形で記憶していくかということが
大事なのかな、なんて思います。
にゃかてぃさんたちの思いと、亡くなった方との絆、
そしてそれを取り巻くいろいろな人たちとの縁が
とても深いように感じました。
なんというか、うまくいえないけど
伝わってくるものがすごく多かったです。
ありがとうございましたm(__)m
コメント ようちゃん2006年11月02日 07:15
>おねさん
コメント、ありがとう!!
ほんとに彼女の死は必然で、関わる人の絆と縁は深いと思います。
残された者はみな、彼女の遺志をこの世で少しでも実現していく使命が
あると切に感じました。
この日には、近江上布の原型となる高宮布を実際に手にとって見れる講演会があったり、スピ仲間が京都のおっちゃん訪問をしたりと、重要なイベントが重なっていた。しかし、連れ合いと子どもを残して、朝早く、名古屋へ向かった。
公立美術館で学芸員をしていた後輩。
追悼の会は美術館の上司とサイクリング部OB有志で企画運営。出席者は当初の予想を遥かに超えて100名余り。そのうち、サイクリング部関係は30名。大学研究室関係、美術館関係、工芸、現代美術の作家などなどが集まる。会場のBGMは後輩コレクションのCDから選曲。事前に送られた計画を見て、この文化レベルの高さについていけるだろうかと少し不安だった。
会場準備のために早めに集まった後輩数名と会場で合流。
あいさつもそこそこに、会場までの道案内係や受付係をきめる。
そうしていると、後輩のご両親が到着。お母さまにはご実家でお会いしたことがある。ごあいさつに行くと「あれから荷物を整理していましたら、サイクリング部の合宿委員の通帳も出てきたんですよ。」とのこと。
そうだ、彼女は合宿委員だったと思い出す。
お父さまとははじめてお会いした。成人式のお祝いに父子2人でヨーロッパ旅行し、昨年末も2人で旅行するほど仲がよかったようだ。ごあいさつすると「大学では周りの人がすごい人ばかりだとよく言ってました。」と返された。そのときはピンとこなかったが、お父さまは娘を京都に出したことをとても後悔されておられたのだった。
---
そうしているうちに、出席者は次々と集まってくる。
私は会場のある階のエレベーターの前でお出迎えしながら、出席者を受付へと誘導。懐かしい顔に思わず何ともいえない親しさがこみあげてくる。
時間にはほとんど出席者がそろい、時間通りに会が始まる。
追悼の場で、見知らぬ者が集っていることもあり、初めは空気が固かった。美術館の上司のはじめの言葉、大学研究室の指導教官、仲間からの言葉、サイクリング部時代の写真上映、仲間からの言葉・・・と進むにつれ場は和み、献杯、会食で一気に交流が始まる。
学生時代の彼女はいつも笑顔で誰にでも親切で、クラブの同輩のOちゃんが語ったように「○○さんはえらいよね~。私もがんばらなくちゃ」といつも謙虚で志が高かった。
研究室では、美学美術の世界ではマイナーな「工藝」の分野に真摯に取り組み、見事に光を当てる研究成果をあげて、彼女は活躍の場を大学から美術館に移した。
クラブの女子部員数名が集っていたところへ、お父さまがごあいさつされた。ここでも再び、後輩がいつも周りの人がすごいと言っていたことに触れ「こんなことを言ってはよくないが、親としては、バカな子でいいから生きていてほしかった」と声をつまらせながら語られた。みんな慰めの言葉をかけようとしたが、私には何も言えなかった。
彼女の訃報に触れて4ヶ月あまり。私はどうやったら乗り越えられるか、試行錯誤した。クラブの集まりの機会を作ったり、メッセージを集めてご実家に送ったり、美術館やご実家を訪問したり、追悼の会の準備に携わったり・・・。その中で、彼女の死をかなり昇華できた気がしていた。
しかし、ご両親はまだまだ娘の死を抱えて生きている。
最後のお父さまの言葉に「娘が亡くなって147日。どうしたらよかったのかと後悔しない日はない」とも。
クラブの同輩たちを見ても整理できてない様子が見える者もいた。後輩の死の重さを改めて感じる。
・・・再び、写真の上映が始まる。
今度は美術館に入ってからの写真である。作家を訪れたり、美術館の展示準備をしたり、イベントのお茶会での着物姿など。
続いて、関わりのあった作家からの言葉。彼女の的確な眼と才能を、周りに支えられながら発揮してきたことが語られる。
後輩は美術館に入り、現代美術にも取り組む。工藝と現代美術、一見すると対極にあるこれらの世界を両方パラレルに的確に見ることができる類稀な逸材であった。
ある作家は”生きているのも辛い状態であるのは分かるけど、それでも生きて彼女の才能を発揮して仕事を残してほしかった”と語った。
後輩の病と才能は切り離すことができないものだったのかもしれない、とふと思いがよぎる。
後輩がお気に入りで通いつめたギャルソンの店員の言葉もあった。後輩の見る眼、語る言葉にとても励まされたとのこと。その様子に、学生時代の彼女が重なった。
後輩は、この世に出る前の才能を見抜き、光を当て、世に出す仕事も数多く行っていた。その中の一人で今はメキシコで活躍する作家のmixiの日記を読んで、後輩は孤独な中で旅立ったのではないと救われた気持ちになったのを思い出す。
会場には、その作家が作ったTシャツを着て出席された方もいらっしゃったことを帰ってきてから知り、追悼の会の場でクラブ関係以外の方々とほとんど交流してなかったことを少し悔いた。
最後に、お父さまの言葉、サイクリング部同輩のAくんの言葉があって、追悼の会は終了した。
お父さまが”年末に娘と旅行したあと、今度は家族みんなで行こうと話していた。娘はいないが、ぜひみんなで行きたい”と語られていたのが、わずかな救いだった。
片づけをして、美術館の上司にあいさつし固い握手を交わして会場をあとにした。
-----
このあと、サイクリング部員の集いがあったが、私は参加せず家路についた。
ぐったりと心身の疲れをひきずりながらたどり着いた我が家の食卓で私を出迎えていたのは、とても食べようとして切ったとは思えない、へたがいくつかに切り取られた不思議な様相のカキだった。
こうして、長い一日が終わった。
次の日記へつづく?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
コメント ようちゃん2006年11月01日 19:33
太陽のウエイブスペルって25日(水)からでした。なぜか土曜が初日だと勘違いしていましたので、日記を一部削除しました。
不思議な様相のカキの秘密は、息子2の伝説として、翌朝、連れ合いから語られたのでした。つづく
おね2006年11月02日 07:09
死は決して失われることのない事実ではあるけれども、
それをどういう形で記憶していくかということが
大事なのかな、なんて思います。
にゃかてぃさんたちの思いと、亡くなった方との絆、
そしてそれを取り巻くいろいろな人たちとの縁が
とても深いように感じました。
なんというか、うまくいえないけど
伝わってくるものがすごく多かったです。
ありがとうございましたm(__)m
コメント ようちゃん2006年11月02日 07:15
>おねさん
コメント、ありがとう!!
ほんとに彼女の死は必然で、関わる人の絆と縁は深いと思います。
残された者はみな、彼女の遺志をこの世で少しでも実現していく使命が
あると切に感じました。
学芸員のお仕事(民具の受け入れ) 2005年07月21日04:00
レイキと出会って 2005年08月01日06:54
勇気づけられたこと 2005年08月10日04:32
レイキ3rd伝授21日目 2005年08月26日21:15
霧の晴れ間 2005年09月22日21:46
博物館での使命の探求 2005年10月07日21:20
レイキと出会って 2005年08月01日06:54
勇気づけられたこと 2005年08月10日04:32
レイキ3rd伝授21日目 2005年08月26日21:15
霧の晴れ間 2005年09月22日21:46
博物館での使命の探求 2005年10月07日21:20
Posted by なかてぃヨーコ at 15:04│Comments(0)
│mixi日記(2005~2013)