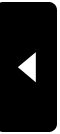2024年01月03日
アートはみんなのもの 2009年02月22日02:40
この土日、米原駅西口すぐの文化産業交流会館で、気軽にどこでもアート交流事業「アートはみんなのもの」を開催しています。
県内の博物館、美術館、文化ホールなどのアートな体験プログラムが一堂にあつまり、無料で自由に参加できるという画期的なイベントです。
うちの博物館は、私が担当で、今日の午後は「水鳥の塗り絵」をやりました。明日の午前は「ヨシ笛づくり」、午後は「綿からの糸紡ぎ」を行います。
広い会場内には、でっかい紙に自由にお絵かきできたり、ダンボール紙の海賊船に乗り込めたり、自分でダンボールでおうちを作ったり、木の枝やどんぐりなどで工作したり、木でからくり細工を作ったり、ペーパークラフトで十一面観音の冠を作ったり、名画を切り貼りして下敷きを作ったり、色紙を自由に切り貼りして自分のお皿を作ったり、甲冑を着て火縄銃を構えたり、蓄音機でレコードを聞けたりなどなど、魅力的なメニュー満載。
うちのやった「水鳥の塗り絵」は、琵琶湖にいるたくさんの水鳥の写真から一つ選び、その鳥の下絵に毛糸、クレヨン、色鉛筆などで自由に色をつけてもらうという単純なプログラムですが、奥が深かった!
写真と同じ色で、はみ出さないように塗れているかどうか・・・
というところに、ついつい大人の目は向いてしまいがちですが、今回参加した子どもたちは、アートで自由な雰囲気の中で、どの子も自分なりに写真から読み取ったものを表現しようとしている。できあがったどの作品からも、そんな「意欲」が感じられました。
いろいろ考えて取り組んで「できた!」と言って作品を見せてくれるときの、ほっとした満足そうな子どもたちの顔。
参加者のお母さん方からは
”子どものこんな姿を見れてよかった。明日も友達を誘ってくるわ。”
という言葉。
こんな瞬間に立ち会えることこそ、私の仕事の醍醐味であり、次の仕事への原動力となるのです。
滋賀県で、子どもたちの学びの環境を変えることができるかもしれない!
という光がはっきりと見えてきました。
こんなアートなプログラムを、学校現場に取り入れる。そのための組織「しが文化芸術学習支援センター」が、今年度からたちあがっています。
10年前に始まった「子どもたちの美術教育をサポートする会」の活動が、嘉田知事の意向で県政の中に位置付けられたのです。
私は4年前にそれに関わり、そのすばらしさに感動していました・・・
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=30900422&owner_id=1010681
プロから学んで茶碗をつくりお茶をいただくこのプログラム、今年度は二つの高校でも行われました。1月の事例報告会で見た記録ビデオの中で、「やんちゃな」生徒たちが、3回の授業を通して別人のように変わっていきました。一緒に見ていたある高校の先生は「生徒たちにこんな機会を与えてやりたい」と泣き崩れました。
今年度、この支援センターが、草木染めをやりたいという養護学校の要望を、私たち「近江はたおり探検隊」につないでくれ、連携授業を行うことができました。生活年齢2~3歳の5人の中学生たちは、初めて出会う探検隊のメンバーとセンターの学生ボランティアを何の垣根もなく受けいれてくれました。一緒に藍の葉をちぎり、カルカヤを刻み・・・。あの時間はなんともいえない、満ち足りたひと時でした。
今回のイベント「アートはみんなのもの」を支えるスタッフも、そんな感動を知っている人たちなのでしょう。
今日のメニュー終了後、手作りカレーを食べながら1時間の交流会がありました。熱い思いをもつ専門家・芸術家が、みんなに楽しみを与え、自分も楽しもうという気持ちで集まっていました。県内にこんなにたくさんの同志がいる・・・と気づけたことは、大きな励みになりました。
あの報告会のとき泣き崩れた高校の先生が、自分の教え子たちをボランティアスタッフに連れてきていました。その高校生たちが”こんな楽しい経験ができるなんて思わなかった。”と口々に語っていたのが印象的でした。
さて、明日(ってもう今日ですが)はヨシ笛と糸紡ぎです。
今年からたちあげた「近江昔くらし倶楽部」のメンバーがスタッフで来てくれます。興味のあるみなさんも、ぜひお越しくださいね~!
^^^^^^^^^^^^^^^^
コメント hirokamo2009年02月22日 12:12
「彩る」という行為は、実はかなり深ーいレベルで
内なるものを揺り動かすものではないか・・と思います。
わたしも以前、カラーリスト養成校でアートセラピーの授業を
担当させてもらったことがありますが、好きな色を選び、好きなように
ただひたすら塗る、というプロセスの中で、皆さんが子供のように
イキイキとしていかれるのを見るのがとても楽しかったです♪
ここ数年はなぜか京都にご縁があるのですが、いずれ地元でも
「色」を媒介して皆さんのお役に立てれば・・と思いますクローバー
コメント ようちゃん2009年02月23日 11:12
hirokamoさ~ん、コメントありがとうございます。
「塗り絵」初めてだったんです。その力にびっくりしました。
「色」の力をきちんと意識して導ける場を作れたら・・・わくわくします。
滋賀のアートはホットですよ。ぜひ一度この世界を体験してみてくださいませ。
最近、ちょっと「五行」に注目しています。
「音」も深そうです。方位や部位や属性、いろんなものを関連づけて、総合的に見ていく視点を忘れないでいたいです。
県内の博物館、美術館、文化ホールなどのアートな体験プログラムが一堂にあつまり、無料で自由に参加できるという画期的なイベントです。
うちの博物館は、私が担当で、今日の午後は「水鳥の塗り絵」をやりました。明日の午前は「ヨシ笛づくり」、午後は「綿からの糸紡ぎ」を行います。
広い会場内には、でっかい紙に自由にお絵かきできたり、ダンボール紙の海賊船に乗り込めたり、自分でダンボールでおうちを作ったり、木の枝やどんぐりなどで工作したり、木でからくり細工を作ったり、ペーパークラフトで十一面観音の冠を作ったり、名画を切り貼りして下敷きを作ったり、色紙を自由に切り貼りして自分のお皿を作ったり、甲冑を着て火縄銃を構えたり、蓄音機でレコードを聞けたりなどなど、魅力的なメニュー満載。
うちのやった「水鳥の塗り絵」は、琵琶湖にいるたくさんの水鳥の写真から一つ選び、その鳥の下絵に毛糸、クレヨン、色鉛筆などで自由に色をつけてもらうという単純なプログラムですが、奥が深かった!
写真と同じ色で、はみ出さないように塗れているかどうか・・・
というところに、ついつい大人の目は向いてしまいがちですが、今回参加した子どもたちは、アートで自由な雰囲気の中で、どの子も自分なりに写真から読み取ったものを表現しようとしている。できあがったどの作品からも、そんな「意欲」が感じられました。
いろいろ考えて取り組んで「できた!」と言って作品を見せてくれるときの、ほっとした満足そうな子どもたちの顔。
参加者のお母さん方からは
”子どものこんな姿を見れてよかった。明日も友達を誘ってくるわ。”
という言葉。
こんな瞬間に立ち会えることこそ、私の仕事の醍醐味であり、次の仕事への原動力となるのです。
滋賀県で、子どもたちの学びの環境を変えることができるかもしれない!
という光がはっきりと見えてきました。
こんなアートなプログラムを、学校現場に取り入れる。そのための組織「しが文化芸術学習支援センター」が、今年度からたちあがっています。
10年前に始まった「子どもたちの美術教育をサポートする会」の活動が、嘉田知事の意向で県政の中に位置付けられたのです。
私は4年前にそれに関わり、そのすばらしさに感動していました・・・
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=30900422&owner_id=1010681
プロから学んで茶碗をつくりお茶をいただくこのプログラム、今年度は二つの高校でも行われました。1月の事例報告会で見た記録ビデオの中で、「やんちゃな」生徒たちが、3回の授業を通して別人のように変わっていきました。一緒に見ていたある高校の先生は「生徒たちにこんな機会を与えてやりたい」と泣き崩れました。
今年度、この支援センターが、草木染めをやりたいという養護学校の要望を、私たち「近江はたおり探検隊」につないでくれ、連携授業を行うことができました。生活年齢2~3歳の5人の中学生たちは、初めて出会う探検隊のメンバーとセンターの学生ボランティアを何の垣根もなく受けいれてくれました。一緒に藍の葉をちぎり、カルカヤを刻み・・・。あの時間はなんともいえない、満ち足りたひと時でした。
今回のイベント「アートはみんなのもの」を支えるスタッフも、そんな感動を知っている人たちなのでしょう。
今日のメニュー終了後、手作りカレーを食べながら1時間の交流会がありました。熱い思いをもつ専門家・芸術家が、みんなに楽しみを与え、自分も楽しもうという気持ちで集まっていました。県内にこんなにたくさんの同志がいる・・・と気づけたことは、大きな励みになりました。
あの報告会のとき泣き崩れた高校の先生が、自分の教え子たちをボランティアスタッフに連れてきていました。その高校生たちが”こんな楽しい経験ができるなんて思わなかった。”と口々に語っていたのが印象的でした。
さて、明日(ってもう今日ですが)はヨシ笛と糸紡ぎです。
今年からたちあげた「近江昔くらし倶楽部」のメンバーがスタッフで来てくれます。興味のあるみなさんも、ぜひお越しくださいね~!
^^^^^^^^^^^^^^^^
コメント hirokamo2009年02月22日 12:12
「彩る」という行為は、実はかなり深ーいレベルで
内なるものを揺り動かすものではないか・・と思います。
わたしも以前、カラーリスト養成校でアートセラピーの授業を
担当させてもらったことがありますが、好きな色を選び、好きなように
ただひたすら塗る、というプロセスの中で、皆さんが子供のように
イキイキとしていかれるのを見るのがとても楽しかったです♪
ここ数年はなぜか京都にご縁があるのですが、いずれ地元でも
「色」を媒介して皆さんのお役に立てれば・・と思いますクローバー
コメント ようちゃん2009年02月23日 11:12
hirokamoさ~ん、コメントありがとうございます。
「塗り絵」初めてだったんです。その力にびっくりしました。
「色」の力をきちんと意識して導ける場を作れたら・・・わくわくします。
滋賀のアートはホットですよ。ぜひ一度この世界を体験してみてくださいませ。
最近、ちょっと「五行」に注目しています。
「音」も深そうです。方位や部位や属性、いろんなものを関連づけて、総合的に見ていく視点を忘れないでいたいです。
学芸員のお仕事(民具の受け入れ) 2005年07月21日04:00
レイキと出会って 2005年08月01日06:54
勇気づけられたこと 2005年08月10日04:32
レイキ3rd伝授21日目 2005年08月26日21:15
霧の晴れ間 2005年09月22日21:46
博物館での使命の探求 2005年10月07日21:20
レイキと出会って 2005年08月01日06:54
勇気づけられたこと 2005年08月10日04:32
レイキ3rd伝授21日目 2005年08月26日21:15
霧の晴れ間 2005年09月22日21:46
博物館での使命の探求 2005年10月07日21:20
Posted by なかてぃヨーコ at 14:47│Comments(0)
│mixi日記(2005~2013)