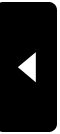2012年02月13日
昔の道具の声を聞いてみよう!(前編)
3学期のこの時期、数多くの小学校3年生が「昔のくらし」の学習をします。
先日、ご縁のある小学校で「昔の道具の声を聞いてみよう」という
出張授業をしてきました。
昔ながらの集落と新しい住宅地が混在する30名の2クラス。
先生との事前打ち合わせのときに、
子どもたちに宿題でおじいちゃん・おばあちゃんから子どもの頃のお話を聞いて、
その結果を送ってくださいとお願いしていたら、
・洗濯物を「川ですすいでいた」
・「火鉢に大きな竹のザルをかぶせて」洗濯物をかわかした
・「箱枕」「しょいこ」「からかさ」をつかっていた
という、今ではなかなか小学生が聞くことができない
一世代か二世代前のくらしの情報がいくつも出てきていて、
びっくりしました。
そこで、感性のある子たちがいるなと直感して、ふと思いついたのが
「昔の道具の声を聞いてみよう」という授業。
博物館に収蔵する体験用の民具の中から、いくつかピックアップし、
子どもたちの前に並べて、自分の選んだ一つの道具について
スケッチしながら、その声を聞こうと心をかたむけてみよう。
というもの。
今までにさまざまな方々に、昔のくらしをめぐって
いろんなお話や実習をしてきましたが、これは、初めてのネタです。
× × ×
学校の先生方からは、座学でなく体験を重視して、
実際に道具を使う体験が求められます。
それを受けて、琵琶湖博物館でも
手押しポンプで水を汲んだり、石臼で粉をひいたり・・・といった
体験プログラムが大人気です。
でも、対応するスタッフが数名必要ですし、
使うことで道具が消耗したり破損したりして維持管理にも手間がかかる。
そもそも、博物館学芸員としては、資料は大切に扱いたいのです。
琵琶湖博物館には一万点にのぼる民具を収蔵しています。
私は開館の年に、民俗学担当の学芸員になって、
初めの仕事がこの民具の整理でした。
一点一点触れながら、クリーニングし、写真を撮り、
法量・重量をはかり、実測図を作り、目録・データベースを作成する
という作業を歴史資料整理室のメンバーとともに何年も行う中で、
民具の声を聞きたいと願いつづけていました。
もともと、民具の専門家ではなかったので、
何に使うかわからないモノも数多く、
本を調べてもわからないものも多々ありました。
しかしじっくりと材料や作り方、使い方のわかる痕跡を見つけながら、
民具と対話して思いを巡らせる楽しさを味わったのです。
「モノを傷つけることなく、しっかり向き合って感じること」は、
民具だけでなく、あらゆる分野の博物館資料に取り組む基本。
博物館の展示物の深い楽しみ方を身につけるためにも、
学芸員が子どもたちにこうした機会をつくるのは意味がある
と思いました。
× × ×
民具を使ってきた生の声をおじいちゃん・おばあちゃんから
聞ける子どもたちなら、
きっと、こんな授業にも、のってくれるに違いない。
そう期待してのチャレンジ。
わくわくどきどきしながら、
洗濯板・たらい(木製)、わら草履・むしろ、火鉢・炭入れ、木桶2つ・天秤棒
を選んで公用車に積んで、小学校へと向かいました。
つづく
先日、ご縁のある小学校で「昔の道具の声を聞いてみよう」という
出張授業をしてきました。
昔ながらの集落と新しい住宅地が混在する30名の2クラス。
先生との事前打ち合わせのときに、
子どもたちに宿題でおじいちゃん・おばあちゃんから子どもの頃のお話を聞いて、
その結果を送ってくださいとお願いしていたら、
・洗濯物を「川ですすいでいた」
・「火鉢に大きな竹のザルをかぶせて」洗濯物をかわかした
・「箱枕」「しょいこ」「からかさ」をつかっていた
という、今ではなかなか小学生が聞くことができない
一世代か二世代前のくらしの情報がいくつも出てきていて、
びっくりしました。
そこで、感性のある子たちがいるなと直感して、ふと思いついたのが
「昔の道具の声を聞いてみよう」という授業。
博物館に収蔵する体験用の民具の中から、いくつかピックアップし、
子どもたちの前に並べて、自分の選んだ一つの道具について
スケッチしながら、その声を聞こうと心をかたむけてみよう。
というもの。
今までにさまざまな方々に、昔のくらしをめぐって
いろんなお話や実習をしてきましたが、これは、初めてのネタです。
× × ×
学校の先生方からは、座学でなく体験を重視して、
実際に道具を使う体験が求められます。
それを受けて、琵琶湖博物館でも
手押しポンプで水を汲んだり、石臼で粉をひいたり・・・といった
体験プログラムが大人気です。
でも、対応するスタッフが数名必要ですし、
使うことで道具が消耗したり破損したりして維持管理にも手間がかかる。
そもそも、博物館学芸員としては、資料は大切に扱いたいのです。
琵琶湖博物館には一万点にのぼる民具を収蔵しています。
私は開館の年に、民俗学担当の学芸員になって、
初めの仕事がこの民具の整理でした。
一点一点触れながら、クリーニングし、写真を撮り、
法量・重量をはかり、実測図を作り、目録・データベースを作成する
という作業を歴史資料整理室のメンバーとともに何年も行う中で、
民具の声を聞きたいと願いつづけていました。
もともと、民具の専門家ではなかったので、
何に使うかわからないモノも数多く、
本を調べてもわからないものも多々ありました。
しかしじっくりと材料や作り方、使い方のわかる痕跡を見つけながら、
民具と対話して思いを巡らせる楽しさを味わったのです。
「モノを傷つけることなく、しっかり向き合って感じること」は、
民具だけでなく、あらゆる分野の博物館資料に取り組む基本。
博物館の展示物の深い楽しみ方を身につけるためにも、
学芸員が子どもたちにこうした機会をつくるのは意味がある
と思いました。
× × ×
民具を使ってきた生の声をおじいちゃん・おばあちゃんから
聞ける子どもたちなら、
きっと、こんな授業にも、のってくれるに違いない。
そう期待してのチャレンジ。
わくわくどきどきしながら、
洗濯板・たらい(木製)、わら草履・むしろ、火鉢・炭入れ、木桶2つ・天秤棒
を選んで公用車に積んで、小学校へと向かいました。
つづく
Posted by なかてぃヨーコ at 10:33│Comments(0)
│昔の道具の声を聞く授業2011