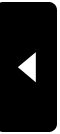2012年02月13日
昔の道具の声を聞いてみよう!(中編)
(前編)よりつづく。
先日、小学校3年生に行った出張授業のお話です。
× × ×
今回の授業をするきっかけを作ってくれた同僚とともに、
小学校の空き教室に、ござを敷いて、
火鉢・炭入れ、たらい・洗濯板、水桶2つ・天秤棒、竹ザル、
そして、ござの横にむしろとわら草履2足をセット。
時間になって、子どもたちが先生に連れられて、
上履きを廊下に脱いでから順々に入室。
ござの上に30人がきちんと並んで座り、先生が私の紹介をして、
いよいよ授業が始まります。
「こんにちは」とあいさつ・自己紹介をし、
子どもたちがおじいちゃん・おばあちゃんからどんなお話を聞いてきたか
軽く振り返って、今日のテーマの発表です。
私「みんな、モノの声って聞いたことあるやろ」
子「えー」
私「机の上の消しゴムとかが落ちたときに「痛い!」とか言うやん」
子「えー、言わへん」
私「そうかなあ。私は博物館にある一万点の道具を一つひとつ見て、
話ができるようになったで」
子「ほんとに?」
私「今日は、みんなにも道具の声を聞いてもらおうと思うんやけど、
やってみる?」
子「うん、やるやる。やりたい!」
私「じゃ、今から道具を紹介するから、自分が声を聞きたいと思う道具を
選んでな」
という調子で、見事に子どもたちはその気になり、
各自選んだ道具の周りに座って、配布されたプリントを各自ボードにはさみ、
準備万端。
・古い大事な道具なので、大切に扱う。
・じっくり観察する。
どんな材料で、どうやって作られ、どうやって使われているか。
それがわかる「あと」をさがす。
いろんな角度から、裏返したりして見る。
・形をスケッチしながら、気づいたことを周りにメモする。
と手順を伝えて、「さあ、はじめ!」
と声をかけると、あちこちで楽しそうに作業が始まりました。
私はそれぞれの道具を回りました。
<むしろ・わら草履チーム>
・わら草履は大事に履いて「ビーサンよりいいわ~」
・むしろに「はだしで歩いていい?」「気持ちいい!」
・わらが、たてとよこに組み合わさってできている。
<火鉢・炭入れチーム>
・火鉢は「あつっ。やけどするわ」「でも、下の方は熱くないな。なんでやろ」
(危ないので同僚に常時ついてもらう)
・粘土で焼いて作っている。(信楽焼の体験があった)
・炭は、木から作られる。(そのまま燃やしたら燃え尽きる。特別な技がある)
<竹ザルチーム>
・竹を割って細くしたものを組み合わせて作ってある。
(見聞きしたり実際にやった経験がある)
・私「どうやって作ってある?」「たての竹の間をよこの竹が上下になって」
私「へえ~、それはわら草履やむしろと同じやなあ」
<たらい・洗濯板チーム>
・「思ったよりも大きかった」(事前に洗濯の今昔比較の学習で写真で見ていた)
・昔はたらい舟として子どもが持ち出して遊ぶこともあった。「入ってみていい?」
・木でできている。一枚でなくたくさんの部品を組み合わせている。
・洗濯板にはくぎも打ってある。「痛かった?」
<水桶・天秤棒チーム>
・たくさんの部品の木でできている。
・「ロープの材料は?」私「シュロ。庭で作ってるおうちもあるよ」
・実際に天秤棒に水桶をさげて運んでみる。
・はんこみたいなものがある。焼印。
私「自分の名前でなく、おうちの名前。自分だけのものでなく、
ご先祖さんから受け継ぎ、子どもたちへ伝える大事なもの」
一通り作業が終わったら、
各チームごとに、私が子どもたちにインタビューしながら
気づいたことを発表してもらい、
今回の道具たちは、
「身近にあるもので、使う人が作ったり直したりしながら、
大事に使われてきたもの」ということを、全体で確認。
最後に、
「道具の声が聞こえたお友だちはいるかな?」と聞いてみたら、
手をあげる子どもたちがいました!
幾人かに発表してもらったのですが、
「たらいが、「前のご主人さまがばらばらにしてしまったけど、
直してくれてうれしかった」と言ってました。」
と言葉を聞けたときは、思わず眼に涙がたまりました。
授業が終わってからも、自分の教室に帰る前に、
たらいに入ったり、水桶をかついだり、むしろをはだしで歩いたり、
している子どもたちもいました。
そっと私に近寄って
「わら草履に「さっきは黙って履いてごめんね」と言ったら「いいよ」と答えてくれた。」
と小さい声ではにかみながら教えてくれた子どももいました。
ほんとに、我ながらいい授業ができたなあとうれしかったです。
先生方にもいい授業だったと喜んでいただけました。
でも、最後まで「声なんて聞こえへんかったわ。聞こうとしたけど」と
悔しそうに大声で怒鳴っていた子どもたちもいたので、
後日、子どもたち宛に手紙を送りました。
つづく
先日、小学校3年生に行った出張授業のお話です。
× × ×
今回の授業をするきっかけを作ってくれた同僚とともに、
小学校の空き教室に、ござを敷いて、
火鉢・炭入れ、たらい・洗濯板、水桶2つ・天秤棒、竹ザル、
そして、ござの横にむしろとわら草履2足をセット。
時間になって、子どもたちが先生に連れられて、
上履きを廊下に脱いでから順々に入室。
ござの上に30人がきちんと並んで座り、先生が私の紹介をして、
いよいよ授業が始まります。
「こんにちは」とあいさつ・自己紹介をし、
子どもたちがおじいちゃん・おばあちゃんからどんなお話を聞いてきたか
軽く振り返って、今日のテーマの発表です。
私「みんな、モノの声って聞いたことあるやろ」
子「えー」
私「机の上の消しゴムとかが落ちたときに「痛い!」とか言うやん」
子「えー、言わへん」
私「そうかなあ。私は博物館にある一万点の道具を一つひとつ見て、
話ができるようになったで」
子「ほんとに?」
私「今日は、みんなにも道具の声を聞いてもらおうと思うんやけど、
やってみる?」
子「うん、やるやる。やりたい!」
私「じゃ、今から道具を紹介するから、自分が声を聞きたいと思う道具を
選んでな」
という調子で、見事に子どもたちはその気になり、
各自選んだ道具の周りに座って、配布されたプリントを各自ボードにはさみ、
準備万端。
・古い大事な道具なので、大切に扱う。
・じっくり観察する。
どんな材料で、どうやって作られ、どうやって使われているか。
それがわかる「あと」をさがす。
いろんな角度から、裏返したりして見る。
・形をスケッチしながら、気づいたことを周りにメモする。
と手順を伝えて、「さあ、はじめ!」
と声をかけると、あちこちで楽しそうに作業が始まりました。
私はそれぞれの道具を回りました。
<むしろ・わら草履チーム>
・わら草履は大事に履いて「ビーサンよりいいわ~」
・むしろに「はだしで歩いていい?」「気持ちいい!」
・わらが、たてとよこに組み合わさってできている。
<火鉢・炭入れチーム>
・火鉢は「あつっ。やけどするわ」「でも、下の方は熱くないな。なんでやろ」
(危ないので同僚に常時ついてもらう)
・粘土で焼いて作っている。(信楽焼の体験があった)
・炭は、木から作られる。(そのまま燃やしたら燃え尽きる。特別な技がある)
<竹ザルチーム>
・竹を割って細くしたものを組み合わせて作ってある。
(見聞きしたり実際にやった経験がある)
・私「どうやって作ってある?」「たての竹の間をよこの竹が上下になって」
私「へえ~、それはわら草履やむしろと同じやなあ」
<たらい・洗濯板チーム>
・「思ったよりも大きかった」(事前に洗濯の今昔比較の学習で写真で見ていた)
・昔はたらい舟として子どもが持ち出して遊ぶこともあった。「入ってみていい?」
・木でできている。一枚でなくたくさんの部品を組み合わせている。
・洗濯板にはくぎも打ってある。「痛かった?」
<水桶・天秤棒チーム>
・たくさんの部品の木でできている。
・「ロープの材料は?」私「シュロ。庭で作ってるおうちもあるよ」
・実際に天秤棒に水桶をさげて運んでみる。
・はんこみたいなものがある。焼印。
私「自分の名前でなく、おうちの名前。自分だけのものでなく、
ご先祖さんから受け継ぎ、子どもたちへ伝える大事なもの」
一通り作業が終わったら、
各チームごとに、私が子どもたちにインタビューしながら
気づいたことを発表してもらい、
今回の道具たちは、
「身近にあるもので、使う人が作ったり直したりしながら、
大事に使われてきたもの」ということを、全体で確認。
最後に、
「道具の声が聞こえたお友だちはいるかな?」と聞いてみたら、
手をあげる子どもたちがいました!
幾人かに発表してもらったのですが、
「たらいが、「前のご主人さまがばらばらにしてしまったけど、
直してくれてうれしかった」と言ってました。」
と言葉を聞けたときは、思わず眼に涙がたまりました。
授業が終わってからも、自分の教室に帰る前に、
たらいに入ったり、水桶をかついだり、むしろをはだしで歩いたり、
している子どもたちもいました。
そっと私に近寄って
「わら草履に「さっきは黙って履いてごめんね」と言ったら「いいよ」と答えてくれた。」
と小さい声ではにかみながら教えてくれた子どももいました。
ほんとに、我ながらいい授業ができたなあとうれしかったです。
先生方にもいい授業だったと喜んでいただけました。
でも、最後まで「声なんて聞こえへんかったわ。聞こうとしたけど」と
悔しそうに大声で怒鳴っていた子どもたちもいたので、
後日、子どもたち宛に手紙を送りました。
つづく
Posted by なかてぃヨーコ at 11:45│Comments(0)
│昔の道具の声を聞く授業2011