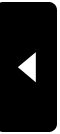2015年03月13日
輪島市門前町黒島地区にある土蔵、移築先を募集中!
今回、草津の解体された小屋の床板を持っていった改築中のお家の
工事を担当している京都の女の大工さんから、
輪島市の土蔵の移築再利用を求めている情報が転送されてきました。
萩野紀一郎さんという方で、能登の里山をあるく・たべる・感じる・あそぶ
「まるやま組」という活動をされています。
http://maruyamagumi.blog102.fc2.com/
今回、能登半島地震を乗り越え、
何度も解体撤去の危機を乗り越えてきた「土蔵」、
現地での再生は難しく、移築して再利用される先を探すことになりました。
建物の写真、簡単な図面はこちら。
建坪3間×5間の15坪で、2階もあわせれば30坪。
土蔵として再生もできますが、倉庫、住宅や店舗などにも使えそうですし、
古材として部分的に活用することもできそうです。
 (PDF: 1181.1KB)
(PDF: 1181.1KB)
× × ×
萩野さんは、私と同じものが見えているのだと思います。
輪島市で、数年前、古民具がたくさんあった旧小学校の木造校舎を利用した
民俗資料館が、維持費削減のため解体されてしまったそうで、
その中の、かやぶきの道具と農具をいくつか、半永久的に借りて、
まるやま組の活動で活用されているそうです。
私は、ほんものの民具は、技の記憶媒体だと思います。
その民具が、機嫌よく使われている状態=よい技、なのだと。
そして、その技こそ、これからの暮らしにとって必要なものなのだと。
だから、ほんものの民具が機能する状態で残っていることが大事だし、
それとともに、民具を実際に使うことが大事だと思います。
(実際に使って、維持管理する技も見つけていくことも重要です)
さらに、萩野さんは、滋賀・守山市の江州左官・土舟の小林隆男さんと
つながっておられました。
小林さんは、「土」のことが大好きで追究し尽くしている若い左官屋さんで、
私は数年前、博物館での仕事がきっかけでお出会いし、
守山の家とご近所だったことがわかり、何度か作業場にお邪魔して
意気投合しました。
今回の土蔵のことを知って、
能登地震の後、崩れた土蔵の修復もやっていると言われていたのを
思い出して、久しぶりに連絡してみようかなと思っていたところでした。
なんだか、萩野さんとは、同志を得たような、不思議な縁を感じます。
× × ×
ということで、この場でも、彼からの依頼のメールを転載させていただきます。
(ご本人の承諾ずみです)
Sent: Tuesday, March 03, 2015 11:09 PM
Subject: 土蔵をどうぞ、土蔵の移築再利用のご案内
みなさま(BCCにて配信しております)
能登三井の萩野紀一郎です。
この3月で能登半島地震から8年、東日本大震災から4年を迎えます。
能登では、地震後のあわただしい修理や解体の嵐が3~4年で過ぎ去り、
表面的には震災の記憶が風化しつつありますが、
まだまだ震災の尾を引いてる問題が残っています。
今日、メールさせていただいたのは、そのひとつです。
実は、輪島市門前町黒島地区にある土蔵、
何度も解体撤去の危機を乗り越えのですが、
ついに現地での再生はあきらめられてしまいました。
傷んでいるところはありますが、きちんと修復すれば十分まだ再生可能です。
是非、どこか別の場所で、新たな形で活用していただけないでしょうか?
建物の写真や簡単な図面は添付の通りです。<※上でリンクしたPDFファイル>
建坪3間×5間の15坪で、2階もあわせれば30坪です。
土蔵として再生することも可能ですが、より簡単に倉庫としても活用可能です。
また、住宅や店舗、その他の用途としても転用できますし、
古材として部分的に活用することも可能です。
解体費用と諸経費、運搬費をご負担いただければ、
建物本体については、特に費用は必要ありません。
新たな場所での建て方や建設費は別途かかります。
解体費用ですが、再利用を前提とする場合は手で壊すので、
諸費用込で、おおよそ300万ほどかと思いますが、
これは、土や雑材の撤去・搬出をどのように行うかによって大きく変動します。
これらの作業を、できるだけワークショップやボランティアなどでやると、
もちろんそれらの運営費や時間と労力はかかりますが、
費用は抑えることができます。
私が保存を勧めた経緯もあり、所有者や地域の方から責任を問われており
何としても、いい解決方法を早急に見出す必要があります。
そのためにも、少しでも情報を広くお知らせしたいので、
このメールと添付資料は、関心のありそうな知り合いの方々に、
大いに転送や配布してください。
なお、現在このような形で、移築して再利用される方を広く探してますが、
もし時間がかかりそうな場合は、せめて手で解体して、材料を保管できるように、
寄付やクラウドファウンディングなどによる資金集めも検討中です。
是非、みなさまからのお問い合わせ、アドヴァイスお寄せください。
萩野 紀一郎 萩野アトリエ / まるやま組
Kiichiro (Kibo) Hagino Hagino Atelier / Maruyama-gumi
kbhagino@gmail.com http://maruyamagumi.blog102.fc2.com/
工事を担当している京都の女の大工さんから、
輪島市の土蔵の移築再利用を求めている情報が転送されてきました。
萩野紀一郎さんという方で、能登の里山をあるく・たべる・感じる・あそぶ
「まるやま組」という活動をされています。
http://maruyamagumi.blog102.fc2.com/
今回、能登半島地震を乗り越え、
何度も解体撤去の危機を乗り越えてきた「土蔵」、
現地での再生は難しく、移築して再利用される先を探すことになりました。
建物の写真、簡単な図面はこちら。
建坪3間×5間の15坪で、2階もあわせれば30坪。
土蔵として再生もできますが、倉庫、住宅や店舗などにも使えそうですし、
古材として部分的に活用することもできそうです。
× × ×
萩野さんは、私と同じものが見えているのだと思います。
輪島市で、数年前、古民具がたくさんあった旧小学校の木造校舎を利用した
民俗資料館が、維持費削減のため解体されてしまったそうで、
その中の、かやぶきの道具と農具をいくつか、半永久的に借りて、
まるやま組の活動で活用されているそうです。
私は、ほんものの民具は、技の記憶媒体だと思います。
その民具が、機嫌よく使われている状態=よい技、なのだと。
そして、その技こそ、これからの暮らしにとって必要なものなのだと。
だから、ほんものの民具が機能する状態で残っていることが大事だし、
それとともに、民具を実際に使うことが大事だと思います。
(実際に使って、維持管理する技も見つけていくことも重要です)
さらに、萩野さんは、滋賀・守山市の江州左官・土舟の小林隆男さんと
つながっておられました。
小林さんは、「土」のことが大好きで追究し尽くしている若い左官屋さんで、
私は数年前、博物館での仕事がきっかけでお出会いし、
守山の家とご近所だったことがわかり、何度か作業場にお邪魔して
意気投合しました。
今回の土蔵のことを知って、
能登地震の後、崩れた土蔵の修復もやっていると言われていたのを
思い出して、久しぶりに連絡してみようかなと思っていたところでした。
なんだか、萩野さんとは、同志を得たような、不思議な縁を感じます。
× × ×
ということで、この場でも、彼からの依頼のメールを転載させていただきます。
(ご本人の承諾ずみです)
Sent: Tuesday, March 03, 2015 11:09 PM
Subject: 土蔵をどうぞ、土蔵の移築再利用のご案内
みなさま(BCCにて配信しております)
能登三井の萩野紀一郎です。
この3月で能登半島地震から8年、東日本大震災から4年を迎えます。
能登では、地震後のあわただしい修理や解体の嵐が3~4年で過ぎ去り、
表面的には震災の記憶が風化しつつありますが、
まだまだ震災の尾を引いてる問題が残っています。
今日、メールさせていただいたのは、そのひとつです。
実は、輪島市門前町黒島地区にある土蔵、
何度も解体撤去の危機を乗り越えのですが、
ついに現地での再生はあきらめられてしまいました。
傷んでいるところはありますが、きちんと修復すれば十分まだ再生可能です。
是非、どこか別の場所で、新たな形で活用していただけないでしょうか?
建物の写真や簡単な図面は添付の通りです。<※上でリンクしたPDFファイル>
建坪3間×5間の15坪で、2階もあわせれば30坪です。
土蔵として再生することも可能ですが、より簡単に倉庫としても活用可能です。
また、住宅や店舗、その他の用途としても転用できますし、
古材として部分的に活用することも可能です。
解体費用と諸経費、運搬費をご負担いただければ、
建物本体については、特に費用は必要ありません。
新たな場所での建て方や建設費は別途かかります。
解体費用ですが、再利用を前提とする場合は手で壊すので、
諸費用込で、おおよそ300万ほどかと思いますが、
これは、土や雑材の撤去・搬出をどのように行うかによって大きく変動します。
これらの作業を、できるだけワークショップやボランティアなどでやると、
もちろんそれらの運営費や時間と労力はかかりますが、
費用は抑えることができます。
私が保存を勧めた経緯もあり、所有者や地域の方から責任を問われており
何としても、いい解決方法を早急に見出す必要があります。
そのためにも、少しでも情報を広くお知らせしたいので、
このメールと添付資料は、関心のありそうな知り合いの方々に、
大いに転送や配布してください。
なお、現在このような形で、移築して再利用される方を広く探してますが、
もし時間がかかりそうな場合は、せめて手で解体して、材料を保管できるように、
寄付やクラウドファウンディングなどによる資金集めも検討中です。
是非、みなさまからのお問い合わせ、アドヴァイスお寄せください。
萩野 紀一郎 萩野アトリエ / まるやま組
Kiichiro (Kibo) Hagino Hagino Atelier / Maruyama-gumi
kbhagino@gmail.com http://maruyamagumi.blog102.fc2.com/
Posted by なかてぃヨーコ at 19:29│Comments(0)