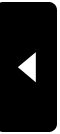2017年01月31日
「たぬきの糸車(1年生)」の授業風景とその後の話
<二年前、2015年1月21日、facebookの投稿より>
今日は、綿入れ半てんに身を包み、
藍染木綿の反物とかせ糸を隠し持ち、
糸車と実棉を携えて、とある小学校の1年生の教室へ。
2クラスの子どもたちが三角すわりして私を迎える。
「うわぁ、いとぐるまやー」
黄色い歓声とともに
きらきらした幾多の眼差しが一瞬にして私を包む。
この、瞳の奥のきらきらを、
どれだけ引き出し続けていけるか。
台本はあってないようなもの。
子どもたち一人ひとりの反応に合わせて、持ち技を繰り出す。
反物を教室の端から端まで広げて、
座っている子どもたちに一列ずつ触れてもらう。
においをかぐ子、裏返す子、ほほの肌触りを確かめる子・・・。
実棉を一つずつ渡して、楽しんでもらい、
「この綿から糸ができるんやで。どうやったらできるやろ」と
全体に投げておいて、
1グループずつ後ろの方に来てもらって、
糸車での糸紡ぎの様子を、聞いて見て感じてもらう。
最後のグループには、指示してないのに
自分なりの糸を作り終えた子もいてびっくり。
糸車で、綿の棒に撚りをかけながら引っ張ると
綿が伸びて糸状になり、
撚り止めしてさらに糸車を回してしっかり撚りをかけると、
あのほわほわの綿が、かたいしっかりした糸になる。
一人ひとりに触って確認してもらうと
「なんでー」「どうしてー」の嵐。
きらきらした瞳は、さらに輝きを増す。
頭を働かせるスイッチが入ったなあ。ふっふっふ。
「その糸をたくさーん作って束にするとこうなるよ」
といって、束にしたかせ糸を見せる。
しばらくの沈黙のあと、
「あ、「糸」や。糸の漢字や」と声があがる。
このやりとり、たまらなく心が喜ぶ、甘美な時間。
最後に、お礼にと、
クラス全員でたぬきの糸車の歌を歌ってくれる。
みんなの心がこもる歌声が、魂に響く。
ご先祖さまが残してくれた、ほんもののモノだからこそ、
ここまで、子どもたちの力を引き出すのだ。
まさに、ご先祖さまから私たちへの宝物。
しかし、その力を知る人は少なく、民具は軽んじられている。
この授業のあと、
たまたま草津市の古いお蔵をつぶすことになったと聞いて、
急遽、駆け付けることになったのだった。(続く?)
・・・・・
このあとの展開は、
このブログのカテゴリー「草津市のお蔵」へとつながるのでした。
http://lbmmukashi.shiga-saku.net/e1118345.html
・・・・・
その翌年も、
同じ学校で「たぬきの糸車」の授業をさせて頂きました。
<一年前、2016年1月29日、facebookの投稿より> ·
1年前の今日、「草津市のお蔵」のことが始まってたんだなぁ。
地元小学校に蔵の中の民具を運び込んだ日、
亀岡の方々も来てくれて、
今回の野鍛冶復活の流れにもつながったんだよなぁ。
そして、その「草津市のお蔵」に出会うきっかけは、
1月下旬の
「1年生にたぬきの糸車の授業をしてほしい」という先生からの電話。
そう、今年も同じ時期に、
同じように依頼があり、今週授業に行ってきました。
すると、そのときに手伝いにきてくれたお母さんのつながりで、
翌日、うまこさんのゲルの中で原始機づくりのワークショップ。
晴れ晴れしい陽光に照らされる草地に、
小さな子どもたち連れの母子が集い、
一人ひとりが楽しむ手づくりのひと時。
ある母親の娘さんが、前日、私の授業を受けていたらしく、
一年生の娘さんが、
「今日は、おかみさんが学校に来てくれて、糸車を見せてくれた。
その糸を使って一年で大人の服一つ分しか布がつくれないから、
大人の服をほどいて、子どもの服にして、
それをほどいて赤ちゃんのおしめにして、そのあと雑巾にして、
そのあと、最後は肥料にした」
と語っていたということを耳にして、感動。
たしかに、35人の子どもたち一人ひとり、
目をキラキラ輝かせながら、私の言うことを聞いてくれていたのは
感じていたけれど、
こうして、自分の伝えたことが、
言葉どおりに周りの方々に伝わっていることを知ることができたのは、
うれしかったなぁ。
持ち寄り材料での、にわか原始機づくりも無事終了し、
ゲルの中での原始機があまりにお似合いでまたやりたいねぇ。
そして、来週も、糸車を抱えて小学校を回り、
新たなお蔵(小屋)との出会いが予定されている~。
・・・・・こうして、ひと時ひと時を、心をこめて生き続け、
その積み重ねで、人生の布を、一糸一糸、織り成していく。
そして、その布の「意外な」美しさに、時折、びっくりする。
織り手は疑いようもなく自分なんだけど、意図してない美しさ。
こういうことがあるから、人生やめられないんだよなぁ(笑)
今日は、綿入れ半てんに身を包み、
藍染木綿の反物とかせ糸を隠し持ち、
糸車と実棉を携えて、とある小学校の1年生の教室へ。
2クラスの子どもたちが三角すわりして私を迎える。
「うわぁ、いとぐるまやー」
黄色い歓声とともに
きらきらした幾多の眼差しが一瞬にして私を包む。
この、瞳の奥のきらきらを、
どれだけ引き出し続けていけるか。
台本はあってないようなもの。
子どもたち一人ひとりの反応に合わせて、持ち技を繰り出す。
反物を教室の端から端まで広げて、
座っている子どもたちに一列ずつ触れてもらう。
においをかぐ子、裏返す子、ほほの肌触りを確かめる子・・・。
実棉を一つずつ渡して、楽しんでもらい、
「この綿から糸ができるんやで。どうやったらできるやろ」と
全体に投げておいて、
1グループずつ後ろの方に来てもらって、
糸車での糸紡ぎの様子を、聞いて見て感じてもらう。
最後のグループには、指示してないのに
自分なりの糸を作り終えた子もいてびっくり。
糸車で、綿の棒に撚りをかけながら引っ張ると
綿が伸びて糸状になり、
撚り止めしてさらに糸車を回してしっかり撚りをかけると、
あのほわほわの綿が、かたいしっかりした糸になる。
一人ひとりに触って確認してもらうと
「なんでー」「どうしてー」の嵐。
きらきらした瞳は、さらに輝きを増す。
頭を働かせるスイッチが入ったなあ。ふっふっふ。
「その糸をたくさーん作って束にするとこうなるよ」
といって、束にしたかせ糸を見せる。
しばらくの沈黙のあと、
「あ、「糸」や。糸の漢字や」と声があがる。
このやりとり、たまらなく心が喜ぶ、甘美な時間。
最後に、お礼にと、
クラス全員でたぬきの糸車の歌を歌ってくれる。
みんなの心がこもる歌声が、魂に響く。
ご先祖さまが残してくれた、ほんもののモノだからこそ、
ここまで、子どもたちの力を引き出すのだ。
まさに、ご先祖さまから私たちへの宝物。
しかし、その力を知る人は少なく、民具は軽んじられている。
この授業のあと、
たまたま草津市の古いお蔵をつぶすことになったと聞いて、
急遽、駆け付けることになったのだった。(続く?)
・・・・・
このあとの展開は、
このブログのカテゴリー「草津市のお蔵」へとつながるのでした。
http://lbmmukashi.shiga-saku.net/e1118345.html
・・・・・
その翌年も、
同じ学校で「たぬきの糸車」の授業をさせて頂きました。
<一年前、2016年1月29日、facebookの投稿より> ·
1年前の今日、「草津市のお蔵」のことが始まってたんだなぁ。
地元小学校に蔵の中の民具を運び込んだ日、
亀岡の方々も来てくれて、
今回の野鍛冶復活の流れにもつながったんだよなぁ。
そして、その「草津市のお蔵」に出会うきっかけは、
1月下旬の
「1年生にたぬきの糸車の授業をしてほしい」という先生からの電話。
そう、今年も同じ時期に、
同じように依頼があり、今週授業に行ってきました。
すると、そのときに手伝いにきてくれたお母さんのつながりで、
翌日、うまこさんのゲルの中で原始機づくりのワークショップ。
晴れ晴れしい陽光に照らされる草地に、
小さな子どもたち連れの母子が集い、
一人ひとりが楽しむ手づくりのひと時。
ある母親の娘さんが、前日、私の授業を受けていたらしく、
一年生の娘さんが、
「今日は、おかみさんが学校に来てくれて、糸車を見せてくれた。
その糸を使って一年で大人の服一つ分しか布がつくれないから、
大人の服をほどいて、子どもの服にして、
それをほどいて赤ちゃんのおしめにして、そのあと雑巾にして、
そのあと、最後は肥料にした」
と語っていたということを耳にして、感動。
たしかに、35人の子どもたち一人ひとり、
目をキラキラ輝かせながら、私の言うことを聞いてくれていたのは
感じていたけれど、
こうして、自分の伝えたことが、
言葉どおりに周りの方々に伝わっていることを知ることができたのは、
うれしかったなぁ。
持ち寄り材料での、にわか原始機づくりも無事終了し、
ゲルの中での原始機があまりにお似合いでまたやりたいねぇ。
そして、来週も、糸車を抱えて小学校を回り、
新たなお蔵(小屋)との出会いが予定されている~。
・・・・・こうして、ひと時ひと時を、心をこめて生き続け、
その積み重ねで、人生の布を、一糸一糸、織り成していく。
そして、その布の「意外な」美しさに、時折、びっくりする。
織り手は疑いようもなく自分なんだけど、意図してない美しさ。
こういうことがあるから、人生やめられないんだよなぁ(笑)
Posted by なかてぃヨーコ at 12:05│Comments(0)
│「たぬきの糸車」授業