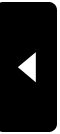2021年01月24日
「たぬきの糸車」授業(2021・花背)
今年もひょんなことから、
新天地・花背で「たぬきの糸車」の授業をさせて頂けることに。
琵琶湖博物館の工房で「近江はたおり探検隊」の道具をお借りして、
当日、綿打ち弓をたすき掛けにし、
右手に糸車、左手に綿繰り機と綿・かせ糸・反物入りの袋と、
いつものフル装備で教室へ。
1,2年生6人の子どもたちと先生2人が迎えてくれる。
私は「おかみさん」役、子どもたちは「たぬき」役。
糸車を回して、綿棒から糸を紡ぎながら、
「今年はたろうの着物を作ってやりたいから、
ああ、どれだけ糸をつむがにゃならんだろう。」とか、
「 春に種をまいて、夏に花が咲いて、綿の実がはじけて、
一つひとつ取って、種をとって、糸に紡いで、機にかけて織って、
反物にして、切って縫うて…。
着物にするまでには、手間がかかるのう。」とか、
独り言の多すぎる、おかみさん(笑)
しずかに糸紡ぎの様子を見終えた、たぬきたちに、
綿の実を一つずつ渡して、感じてもらう。
「なんか入ってる」
「たね?」
「とってみていいよ」
1分、2分、3分…。なかなかきれいにとれない。
そこへ、綿繰り機、登場。
綿を繰って一瞬で種がとれ、弓で打って、ほぐしていく。
「うわあ~」とあちこちから声があがる。
子どもたちの意欲・興味に共鳴しながら、展開していく。
45分、あっという間に終わる。
勤める森のほいくしょに戻って、若き同僚に、
子どもたちにも見せてやりたいなあ、と相談すると、
見たいかどうか、子どもたちに聞いてくれた。
年長さん全員が「見てみたい!」と意欲的な返事。
そこで、再び、フル装備で子どもたちの前へ。
つかみは、出欠シール帳の今月のページ「つるのおんがえし」
ロールケーキのような反物のシール。
「これのほんものは、これやで」と実物を出して、
端っこの糸の組み合ってる部分を見てもらう。
「糸やな」
「糸って、どうやってできてるんやろ?」
「これからできてるんやけどな」
綿の実を一人一人に手渡す。
さわって感じる子どもたちの前で、
綿を繰り、弓で打ち、綿棒を作り、糸車で糸を紡ぐ。
「うわあ~」「なんで~」「すごい~」と声があがる。
そんな様子を横目で見ながら、種を手で取り続け、
全部きれいに取り切った子が2人も。
10分以上かかったんじゃないかな。
その子が、綿打ちもしたい、と切望するので、
特別に、みんなが見る中、支度して手ほどき。
仲間が打つ姿を見て、「わたしも」「ぼくも」と火が付いた。
次の子に支度して「どうぞ」
でも、まったく動けない。
「おともだちに教えてたとき、見てたでしょ。
自分もやるつもりで本気で見てほしい。私は教えない。技はぬすむもの!」
暮らしの手業は「教えてもらってないからできません」では済まされない。
人生の大先輩たちは、そうやって身につけてきたのだ。
× × ×
私は、こんな、ご先祖さまから伝えられたモノ・コトを、
子どもたちと交歓するひと時が、たまらなく嬉しい人なのだ。
学芸員辞めてからも、オファーがあればどこへでも。
→1年生「たぬきの糸車」(2015,2016年)
https://lbmmukashi.shiga-saku.net/c53985.html
(去年、一昨年は、葛川で「たぬきの糸車」)
博物館学芸員、現役の頃は、こんな授業まで。
→3年生「昔の道具の声を聞いてみよう!」(2011年)
https://lbmmukashi.shiga-saku.net/e745779.html
こんな過去の実践に改めて触れてみて、
私は、ずーと、ぶれずにやってきたんだなあ、と思う。
「新米保育士」であってもなお、こうした機会を与えて頂け、
忘れかけてた自分の大切な部分を取り戻した出来事に深謝!
新天地・花背で「たぬきの糸車」の授業をさせて頂けることに。
琵琶湖博物館の工房で「近江はたおり探検隊」の道具をお借りして、
当日、綿打ち弓をたすき掛けにし、
右手に糸車、左手に綿繰り機と綿・かせ糸・反物入りの袋と、
いつものフル装備で教室へ。
1,2年生6人の子どもたちと先生2人が迎えてくれる。
私は「おかみさん」役、子どもたちは「たぬき」役。
糸車を回して、綿棒から糸を紡ぎながら、
「今年はたろうの着物を作ってやりたいから、
ああ、どれだけ糸をつむがにゃならんだろう。」とか、
「 春に種をまいて、夏に花が咲いて、綿の実がはじけて、
一つひとつ取って、種をとって、糸に紡いで、機にかけて織って、
反物にして、切って縫うて…。
着物にするまでには、手間がかかるのう。」とか、
独り言の多すぎる、おかみさん(笑)
しずかに糸紡ぎの様子を見終えた、たぬきたちに、
綿の実を一つずつ渡して、感じてもらう。
「なんか入ってる」
「たね?」
「とってみていいよ」
1分、2分、3分…。なかなかきれいにとれない。
そこへ、綿繰り機、登場。
綿を繰って一瞬で種がとれ、弓で打って、ほぐしていく。
「うわあ~」とあちこちから声があがる。
子どもたちの意欲・興味に共鳴しながら、展開していく。
45分、あっという間に終わる。
勤める森のほいくしょに戻って、若き同僚に、
子どもたちにも見せてやりたいなあ、と相談すると、
見たいかどうか、子どもたちに聞いてくれた。
年長さん全員が「見てみたい!」と意欲的な返事。
そこで、再び、フル装備で子どもたちの前へ。
つかみは、出欠シール帳の今月のページ「つるのおんがえし」
ロールケーキのような反物のシール。
「これのほんものは、これやで」と実物を出して、
端っこの糸の組み合ってる部分を見てもらう。
「糸やな」
「糸って、どうやってできてるんやろ?」
「これからできてるんやけどな」
綿の実を一人一人に手渡す。
さわって感じる子どもたちの前で、
綿を繰り、弓で打ち、綿棒を作り、糸車で糸を紡ぐ。
「うわあ~」「なんで~」「すごい~」と声があがる。
そんな様子を横目で見ながら、種を手で取り続け、
全部きれいに取り切った子が2人も。
10分以上かかったんじゃないかな。
その子が、綿打ちもしたい、と切望するので、
特別に、みんなが見る中、支度して手ほどき。
仲間が打つ姿を見て、「わたしも」「ぼくも」と火が付いた。
次の子に支度して「どうぞ」
でも、まったく動けない。
「おともだちに教えてたとき、見てたでしょ。
自分もやるつもりで本気で見てほしい。私は教えない。技はぬすむもの!」
暮らしの手業は「教えてもらってないからできません」では済まされない。
人生の大先輩たちは、そうやって身につけてきたのだ。
× × ×
私は、こんな、ご先祖さまから伝えられたモノ・コトを、
子どもたちと交歓するひと時が、たまらなく嬉しい人なのだ。
学芸員辞めてからも、オファーがあればどこへでも。
→1年生「たぬきの糸車」(2015,2016年)
https://lbmmukashi.shiga-saku.net/c53985.html
(去年、一昨年は、葛川で「たぬきの糸車」)
博物館学芸員、現役の頃は、こんな授業まで。
→3年生「昔の道具の声を聞いてみよう!」(2011年)
https://lbmmukashi.shiga-saku.net/e745779.html
こんな過去の実践に改めて触れてみて、
私は、ずーと、ぶれずにやってきたんだなあ、と思う。
「新米保育士」であってもなお、こうした機会を与えて頂け、
忘れかけてた自分の大切な部分を取り戻した出来事に深謝!
ローカル七十二候 第64~72候(冬至・小寒・大寒)
ローカル七十二候 第55~63候(立冬・小雪・大雪)
ローカル七十二候 第46~54候(秋分・寒露・霜降)
ローカル七十二候 第37~45候(立秋・処暑・白露)
ローカル七十二候 第28~36候(夏至・小暑・大暑)
ローカル七十二候 第19~27候(立夏・小満・芒種)
ローカル七十二候 第55~63候(立冬・小雪・大雪)
ローカル七十二候 第46~54候(秋分・寒露・霜降)
ローカル七十二候 第37~45候(立秋・処暑・白露)
ローカル七十二候 第28~36候(夏至・小暑・大暑)
ローカル七十二候 第19~27候(立夏・小満・芒種)