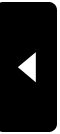2012年01月08日
「近江昔くらし倶楽部」の取り組み
『里海の自然と生活』では冨江家のくらしの紹介の続きに
「近江昔くらし倶楽部の取り組み」についてもまとめているので、
その部分もここに掲載いたします。
#快諾くださったみずのわ出版さまに感謝します!
× × ×
5 おわりに-「近江昔くらし倶楽部」の取り組み
こうした冨江家の展示を含め、近江の伝統的な暮らしぶりを調べていくうちに、
そこには現代の暮らしでは忘れ去られた合理性があることに気づかされる。
それは、自然の理にかない無理がなく、無駄にしない(ゴミの出ない)、
身近なもので成り立たせる暮らしぶりである。
そこで、こうした「かつて」の暮らしから学び、実際にその断片を体験して、
「いま」の暮らしを見直して、「これから」の暮らしに役立てていくことを目的に、
はしかけグループ「近江昔くらし倶楽部」を立ち上げて活動を進めている。
琵琶湖博物館には、地域の人々が博物館で
自分たちの活動を自発的に行うことができる「はしかけ制度」があり、
うおの会、ほねほねクラブ、たんさいぼうの会、湖をつなぐ会、里山の会など、
15のグループが活動している。
「近江昔くらし倶楽部」はその内の一つである。
活動の主な舞台は、琵琶湖博物館の屋外展示にある「生活実験工房」という
民家風の建物と田畑・森(写真9)。

生活実験工房は、囲炉裏、かまど、土間、和室といった伝統的な日本家屋の
しつらえとともに、水道・ガスやエアコンも完備している現代住宅であり、
「かつて」と「いま」を比べるには絶好の建物である。
ここを拠点にして、滋賀の伝統作物など田畑で栽培し、
昔ながらの道具を使って、伝統的な加工方法で衣食住の暮らしの断片を再現している。
田んぼでは羽二重餅とシシクワズを苗代づくりから栽培、収穫して脱穀まで行い、
餅つきやワラで注連飾り・草履づくりも行う。
畑では、和棉、青花、藍などの染織素材を栽培し、藍染木綿の復元製作を行ったり、
山田のねずみ大根、矢島かぶ、日野菜などを栽培して漬物を作ったり、
さらに、森の中で柴刈りをして工房での煮炊きに使ったりもする。
意欲ある大人・子ども、専門家の力合わせながら、冨江家から学び、
こうした小地域循環型の暮らしを少しずつ実験的に進めている。
今回の琵琶湖での採藻調査の結果も、ぜひ「近江昔くらし倶楽部」の活動で活かしてみたい。
生活実験工房のすぐ先が琵琶湖であり、大変都合がよい。
自然農法をやっている方から琵琶湖の水草は肥料として使いよいと聞き、
試しに自宅の菜園で使ってみたら、分解の早さも適当で、
陸の草のように雑草が芽吹くこともなく非常に使いよかった。
こうした体験活動の積み重ねが、参加者の価値観や意識を変える
大きなきっかけになっている手ごたえを感じている。
今後も活動を継続していくことで、あるもので成り立たせる技や工夫、
道具を修理しながら使い続ける知恵、無駄なことを避けて無理をしない姿勢、
みんなでわかちあう心が育まれ、自然と共生する暮らしが実現できたらと願っている。
最後に蛇足だが、
この工房に隣接したトイレには、世界の尻ふき具の展示がある。
琵琶湖の水草を尻ふき具として使った話は聞いたことがないが、
トイレの各個室に、トウモロコシの皮など世界中のいろんなトイレットペーパーの
代用品の展示がされている。
日本のトイレの歴史や世界のトイレの工夫の展示もあるので、
来館の際はぜひ足をのばしてみてほしい。
× × ×
【出典】
印南敏秀編,『里海の自然と生活-海・湖資源の過去・現在・未来』,みずのわ出版,2011
http://www.mizunowa.com/book/book-shousai/satoumi2.html
Ⅱ 湖・海の藻の過去・現在・未来
五 琵琶湖の水草利用と生活世界-多様な既存資料と琵琶湖博物館の紹介から
中藤容子
のうち271-273頁を抜粋
「近江昔くらし倶楽部の取り組み」についてもまとめているので、
その部分もここに掲載いたします。
#快諾くださったみずのわ出版さまに感謝します!
× × ×
5 おわりに-「近江昔くらし倶楽部」の取り組み
こうした冨江家の展示を含め、近江の伝統的な暮らしぶりを調べていくうちに、
そこには現代の暮らしでは忘れ去られた合理性があることに気づかされる。
それは、自然の理にかない無理がなく、無駄にしない(ゴミの出ない)、
身近なもので成り立たせる暮らしぶりである。
そこで、こうした「かつて」の暮らしから学び、実際にその断片を体験して、
「いま」の暮らしを見直して、「これから」の暮らしに役立てていくことを目的に、
はしかけグループ「近江昔くらし倶楽部」を立ち上げて活動を進めている。
琵琶湖博物館には、地域の人々が博物館で
自分たちの活動を自発的に行うことができる「はしかけ制度」があり、
うおの会、ほねほねクラブ、たんさいぼうの会、湖をつなぐ会、里山の会など、
15のグループが活動している。
「近江昔くらし倶楽部」はその内の一つである。
活動の主な舞台は、琵琶湖博物館の屋外展示にある「生活実験工房」という
民家風の建物と田畑・森(写真9)。

生活実験工房は、囲炉裏、かまど、土間、和室といった伝統的な日本家屋の
しつらえとともに、水道・ガスやエアコンも完備している現代住宅であり、
「かつて」と「いま」を比べるには絶好の建物である。
ここを拠点にして、滋賀の伝統作物など田畑で栽培し、
昔ながらの道具を使って、伝統的な加工方法で衣食住の暮らしの断片を再現している。
田んぼでは羽二重餅とシシクワズを苗代づくりから栽培、収穫して脱穀まで行い、
餅つきやワラで注連飾り・草履づくりも行う。
畑では、和棉、青花、藍などの染織素材を栽培し、藍染木綿の復元製作を行ったり、
山田のねずみ大根、矢島かぶ、日野菜などを栽培して漬物を作ったり、
さらに、森の中で柴刈りをして工房での煮炊きに使ったりもする。
意欲ある大人・子ども、専門家の力合わせながら、冨江家から学び、
こうした小地域循環型の暮らしを少しずつ実験的に進めている。
今回の琵琶湖での採藻調査の結果も、ぜひ「近江昔くらし倶楽部」の活動で活かしてみたい。
生活実験工房のすぐ先が琵琶湖であり、大変都合がよい。
自然農法をやっている方から琵琶湖の水草は肥料として使いよいと聞き、
試しに自宅の菜園で使ってみたら、分解の早さも適当で、
陸の草のように雑草が芽吹くこともなく非常に使いよかった。
こうした体験活動の積み重ねが、参加者の価値観や意識を変える
大きなきっかけになっている手ごたえを感じている。
今後も活動を継続していくことで、あるもので成り立たせる技や工夫、
道具を修理しながら使い続ける知恵、無駄なことを避けて無理をしない姿勢、
みんなでわかちあう心が育まれ、自然と共生する暮らしが実現できたらと願っている。
最後に蛇足だが、
この工房に隣接したトイレには、世界の尻ふき具の展示がある。
琵琶湖の水草を尻ふき具として使った話は聞いたことがないが、
トイレの各個室に、トウモロコシの皮など世界中のいろんなトイレットペーパーの
代用品の展示がされている。
日本のトイレの歴史や世界のトイレの工夫の展示もあるので、
来館の際はぜひ足をのばしてみてほしい。
× × ×
【出典】
印南敏秀編,『里海の自然と生活-海・湖資源の過去・現在・未来』,みずのわ出版,2011
http://www.mizunowa.com/book/book-shousai/satoumi2.html
Ⅱ 湖・海の藻の過去・現在・未来
五 琵琶湖の水草利用と生活世界-多様な既存資料と琵琶湖博物館の紹介から
中藤容子
のうち271-273頁を抜粋
Posted by なかてぃヨーコ at 15:48│Comments(0)
│「近江昔くらし倶楽部」とは