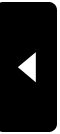2009年07月02日
特別研究セミナーの振り返りと今後の木考塾との協働
「住まいの小学校」をはじめることになった経緯として、
あげておきます。
-------
●第53回特別研究セミナー(2009年3月27日開催)の報告
□テーマ:『資源が循環するこれからの住まいと暮らし』
-これをテーマに博物館と何ができるか-
・参加者50名(内、学芸職員12名、木考塾会員15名の参加に加え、
はしかけ会員とその周辺の方々12名。
・セミナーに先立ち、常設展示の冨江家、丸子船の説明会を開催。
休憩時間には地域材のコースターに地元作の和菓子とお茶を楽しんだ。
討論ではさまざまな立場からの意見が出され、立場の違いが共有される
協働のキックオフにふさわしい場になった。
以下、出された意見の一部。
・木考塾、博物館職員、その他の方々が参加し、意見交換できたことで、
思いがけない気づきがあった。
・専門的なことをいかにわかりやすく伝えるかが難しい。
・今回、伝えたいことがきちんと伝わっているだろうか疑問。
・「伝統構法」の語は誤解を与えやすい。きちんと定義する。
不用意に使わない方がいい。
・学芸員の世界と建築の世界は、全く違った価値観。
だからこそ、いっしょにやる意味がある。
・学芸員の世界につながることを我々はやっていると伝えたい。
・学芸員は「事実を提示し見るものに考えてもらう」という展示思想。
それでほんとうによいのか。
・一般の方はこれからも意見交換できる場を続けてほしいと期待している。
・我々の目的は何か。その共通の目的に向かって、お互いができることを
やっていくことこそ大事。
・「資源が循環するこれからの住まいと暮らし」へ向かうことこそ、
われわれの目的ではないか。
●今後についての木考塾とのミーティング結果(博物館で行う具体的な事業内容)
□当面始めること:共同例会「住まいの小学校」
・木考塾と博物館のはしかけグループ「近江昔くらし倶楽部」とで定期的な例会を開く。
テーマは「住まいの今から暮らしを考える」
・木考塾のメンバーがつくった家(特殊なものではなく、一般レベルのもの)の報告
をする。建築に際してこだわった部分やできなかった部分、さらにそれがその後の
暮らしの中でどのような影響を与えたか(リサーチするか建築主に参加してもらう。)
に触れる。報告を口火に、参加者が自由に今の住まいと暮らしについて語り合う。
・原則として2ヶ月に一度、博物館の生活実験工房の和室・土間で開催
(実際に建てたお家で開催も?)
・毎回、記録をとって、報告書にしていく。
(「住まいの小学校」のWebページにも記録を掲載する。)
□次なる目標「集う・使う・創る新空間での展示」
今後、話し合う。
□最終目標:博物館企画展示室に住まいの「かつて」「いま」「これから」の
それぞれのモデルを建て、体験してもらう。
(エネルギー消費量、CO2排出量、資源の循環の観点からの情報も加える)
モデルや展示パネルは巡回可能な形式にしておくと、各地で巡回展示が可能。
----------
あげておきます。
-------
●第53回特別研究セミナー(2009年3月27日開催)の報告
□テーマ:『資源が循環するこれからの住まいと暮らし』
-これをテーマに博物館と何ができるか-
・参加者50名(内、学芸職員12名、木考塾会員15名の参加に加え、
はしかけ会員とその周辺の方々12名。
・セミナーに先立ち、常設展示の冨江家、丸子船の説明会を開催。
休憩時間には地域材のコースターに地元作の和菓子とお茶を楽しんだ。
討論ではさまざまな立場からの意見が出され、立場の違いが共有される
協働のキックオフにふさわしい場になった。
以下、出された意見の一部。
・木考塾、博物館職員、その他の方々が参加し、意見交換できたことで、
思いがけない気づきがあった。
・専門的なことをいかにわかりやすく伝えるかが難しい。
・今回、伝えたいことがきちんと伝わっているだろうか疑問。
・「伝統構法」の語は誤解を与えやすい。きちんと定義する。
不用意に使わない方がいい。
・学芸員の世界と建築の世界は、全く違った価値観。
だからこそ、いっしょにやる意味がある。
・学芸員の世界につながることを我々はやっていると伝えたい。
・学芸員は「事実を提示し見るものに考えてもらう」という展示思想。
それでほんとうによいのか。
・一般の方はこれからも意見交換できる場を続けてほしいと期待している。
・我々の目的は何か。その共通の目的に向かって、お互いができることを
やっていくことこそ大事。
・「資源が循環するこれからの住まいと暮らし」へ向かうことこそ、
われわれの目的ではないか。
●今後についての木考塾とのミーティング結果(博物館で行う具体的な事業内容)
□当面始めること:共同例会「住まいの小学校」
・木考塾と博物館のはしかけグループ「近江昔くらし倶楽部」とで定期的な例会を開く。
テーマは「住まいの今から暮らしを考える」
・木考塾のメンバーがつくった家(特殊なものではなく、一般レベルのもの)の報告
をする。建築に際してこだわった部分やできなかった部分、さらにそれがその後の
暮らしの中でどのような影響を与えたか(リサーチするか建築主に参加してもらう。)
に触れる。報告を口火に、参加者が自由に今の住まいと暮らしについて語り合う。
・原則として2ヶ月に一度、博物館の生活実験工房の和室・土間で開催
(実際に建てたお家で開催も?)
・毎回、記録をとって、報告書にしていく。
(「住まいの小学校」のWebページにも記録を掲載する。)
□次なる目標「集う・使う・創る新空間での展示」
今後、話し合う。
□最終目標:博物館企画展示室に住まいの「かつて」「いま」「これから」の
それぞれのモデルを建て、体験してもらう。
(エネルギー消費量、CO2排出量、資源の循環の観点からの情報も加える)
モデルや展示パネルは巡回可能な形式にしておくと、各地で巡回展示が可能。
----------
2/17・3/10 環境ほっとカフェ「未来(これから)のくらしの作り方」
11/23.24の展開と11/25博物館リニューアル県民ワークショップ
4/21-5/3「湖国の布~麻・絹・綿~」のご案内
「近江スローライフの会1周年記念 小縁日・交流会」のご案内
「病気の原因は食歴にある」
9/17~19・愛荘町で藍麻SHOWのお知らせ
11/23.24の展開と11/25博物館リニューアル県民ワークショップ
4/21-5/3「湖国の布~麻・絹・綿~」のご案内
「近江スローライフの会1周年記念 小縁日・交流会」のご案内
「病気の原因は食歴にある」
9/17~19・愛荘町で藍麻SHOWのお知らせ