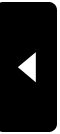2012年07月19日
工房通信2012.8-9月号
工房通信
琵琶湖博物館はしかけグループ「近江昔くらし倶楽部」のはしかけニューズレターの内容を
中心にしながら、「近江はたおり探検隊」や生活実験工房で行われる活動をお知らせします。
#はしかけ制度・ニューズレターはこちら
http://www.lbm.go.jp/hashikake/index.html
近江昔くらし倶楽部
【活動報告日の活動会員数(のべ) 25名(内子ども7名) 】
グループ代表アドレス:mukashi@lbm.go.jp グループ担当者:中藤容子
毎度ながら私ごとで失礼します。先日、昔のくらしから知る省エネのこつについて、
NHK大津放送局から取材させてほしいと電話がありました。
近江昔くらし倶楽部のブログをごらんになったようです。
私が博物館の農村のくらしを案内し、帰宅して家事をしている様子を撮影したいと
いう企画書が届きました。月曜の休館日に撮影、そして、夕方のローカルニュースの
中で放映されました。
(NHK大津放送局「おうみ探検隊」のインターネットページにも掲載されています。)
省エネのヒントを古民家ぐらしから学ぶ
http://www.nhk.or.jp/otsu/program/610/tanken/20120711.html
<なんだか前回とほとんど同じですね(笑)>
その翌日、米原で湖北農村女性活動グループの方々と交流する機会がありました。
50年来、地元で農産物を使った商品開発に取り組んでこられた人生の先輩方と
地元で子育てしながらそれを受け継ごうとされる若妻たちとともに、
インドのラダック地方のくらしの移り変わりを描く「懐かしい未来」の映像を見て、
お互いに語りあいました。
ラダックでは何世代にもわたって、村の人々が助け合い、自然なペースで歌いながら
作業していたくらしがありましたが、数年で一変します。
賃労働のために男の人は街へ、子どもは学校へ出ていき、
残された女たちが家畜の世話と農作業を担う。お金を出さないと誰も手伝ってくれない。
学校で学んだ子どもたちのほとんどは街の仕事にありつけず、
かといって村に戻ってきても暮らしの技も身につけてない。
「この村には貧しい家はない」と語っていた若者が、数年後に
「先進国の援助があればもっと豊かに暮らせるのに」と語るほど、
人々の心もくらしも変わってしまうのです。
湖北の人生の先輩方は「自分たちとまったく同じだ」と、ご自分の人生をふりかえって
語ってくださいました。それを若妻たちとともに重く受け止めました。
ラダックでは、「懐かしい未来」の活動をされるヘレナさんが応援して、女性たちが
力を合わせて、自分たちの暮らしを外国人に紹介するツアーを企画・運営しはじめました。
自然の理にかなう暮らしぶりを学びに外国からくる人々と交わることで、
ラダックの人々は誇りを取り戻し始めています。
湖北・滋賀に残る自然の理にかなう暮らしぶりも、世界中の方々が学ぶ価値を
もっていると思います。琵琶湖博物館の冨江家のくらしも「世界に誇れる」くらしです。
縁あるみなさんとともに、その価値を掘り起こして、伝えていきたいと改めて思いました。
【活動報告】
工房を楽しもう!
■ 6月20日(水)、(参加者4名)
小麦粉から手打ちしてうどんをつくりました。Oさんの持ってきてくださったつゆで、
はたおり探検隊の方々とともにいただきました。
古民家くらし体験(お馬と畑・奥加河荘)
■ 6月6日(木)、7月8日(日) (のべ参加者17名(内子ども7人))
6月は金星の日面通過や雑穀畑の草取り、整体を楽しみました。
岐阜・加子母もりのいえのMさんや岡山からの親子の参加者もあって賑やかでした。
7月は雑穀畑の草取りのあと、お馬に乗りました。
古民家くらし体験(葛川かや葺きの家)
■ 6月21日(木)、 (参加者4名)
夏至のこの日、囲炉裏を囲んでおしゃべりしながら手仕事しました。
13の月の暦が話題にあがりました。
【活動予定】
特に明記しているもの以外は、申し込み不要、参加費無料です。
必要なものはみんなで持ち寄りましょう。
工房を楽しもう!
8、9月はお休みします。
□「工房田んぼ行事」(生活実験工房主催)
■8月18日(土)かかしづくり ■9月29日(土)稲刈り
いずれも10時~12時 屋外展示・生活実験工房にて
□「織姫の会」(近江はたおり探検隊主催)
古民家くらし体験 (お馬と畑・奥加河荘)
馬と鶏、犬猫を一緒に放し飼いにしている大津市大石富川のYさん宅を訪ねて、
雑穀畑や家の作業をしたり、改装した古民家の空間を楽しんだりします。
作業できる服装、お弁当持参です。参加希望の方は中藤まで。
■ 8月8日(水) 10時半-14時半
■ 9月20日(木) (水) 11時-14時半
■ 10月29日(月) 11時-14時半
古民家くらし体験 (葛川かや葺きの家)
移築した古民家「葛川かや葺きの家」(大津市葛川坊村町)で、糸づくりや繕い物、
ヨシ笛・草履などの細工づくりなど、古民家の空間に手仕事を持ち込んで
楽しく作業しましょう。手仕事の道具、お弁当持参です。
(今年は二十四節気を意識した日程に開催します。)
■ 9月6日(木)(「百露」の前日) 10時半-15時
おうみ昔くらし探検塾
滋賀県の昔ながらの衣食住から学び、これからのくらしに活かしていくきっかけの場として、
年間6回、参加者同士で学びあいます。
はしかけ「近江昔くらし倶楽部」の方々はスタッフとして参加ください。(参加される方は事前連絡ください。)
※時間はいずれも10:00-15:00です。
■ 9月8日(土) 綿から着物をつくるくらし 場所:生活実験工房(共催:びわたん)
■ 10月28日(日) イネを育てるくらし 場所:生活実験工房
■ 1月20日(日) 里山体験教室に参加する 場所:野洲市大篠原(共催:里山の会) 参加費:100円(保険料含む)
■ 3月16日(土) 昔のくらしから学びあう 場所:生活実験工房
琵琶湖博物館はしかけグループ「近江昔くらし倶楽部」のはしかけニューズレターの内容を
中心にしながら、「近江はたおり探検隊」や生活実験工房で行われる活動をお知らせします。
#はしかけ制度・ニューズレターはこちら
http://www.lbm.go.jp/hashikake/index.html
近江昔くらし倶楽部
【活動報告日の活動会員数(のべ) 25名(内子ども7名) 】
グループ代表アドレス:mukashi@lbm.go.jp グループ担当者:中藤容子
毎度ながら私ごとで失礼します。先日、昔のくらしから知る省エネのこつについて、
NHK大津放送局から取材させてほしいと電話がありました。
近江昔くらし倶楽部のブログをごらんになったようです。
私が博物館の農村のくらしを案内し、帰宅して家事をしている様子を撮影したいと
いう企画書が届きました。月曜の休館日に撮影、そして、夕方のローカルニュースの
中で放映されました。
(NHK大津放送局「おうみ探検隊」のインターネットページにも掲載されています。)
省エネのヒントを古民家ぐらしから学ぶ
http://www.nhk.or.jp/otsu/program/610/tanken/20120711.html
<なんだか前回とほとんど同じですね(笑)>
その翌日、米原で湖北農村女性活動グループの方々と交流する機会がありました。
50年来、地元で農産物を使った商品開発に取り組んでこられた人生の先輩方と
地元で子育てしながらそれを受け継ごうとされる若妻たちとともに、
インドのラダック地方のくらしの移り変わりを描く「懐かしい未来」の映像を見て、
お互いに語りあいました。
ラダックでは何世代にもわたって、村の人々が助け合い、自然なペースで歌いながら
作業していたくらしがありましたが、数年で一変します。
賃労働のために男の人は街へ、子どもは学校へ出ていき、
残された女たちが家畜の世話と農作業を担う。お金を出さないと誰も手伝ってくれない。
学校で学んだ子どもたちのほとんどは街の仕事にありつけず、
かといって村に戻ってきても暮らしの技も身につけてない。
「この村には貧しい家はない」と語っていた若者が、数年後に
「先進国の援助があればもっと豊かに暮らせるのに」と語るほど、
人々の心もくらしも変わってしまうのです。
湖北の人生の先輩方は「自分たちとまったく同じだ」と、ご自分の人生をふりかえって
語ってくださいました。それを若妻たちとともに重く受け止めました。
ラダックでは、「懐かしい未来」の活動をされるヘレナさんが応援して、女性たちが
力を合わせて、自分たちの暮らしを外国人に紹介するツアーを企画・運営しはじめました。
自然の理にかなう暮らしぶりを学びに外国からくる人々と交わることで、
ラダックの人々は誇りを取り戻し始めています。
湖北・滋賀に残る自然の理にかなう暮らしぶりも、世界中の方々が学ぶ価値を
もっていると思います。琵琶湖博物館の冨江家のくらしも「世界に誇れる」くらしです。
縁あるみなさんとともに、その価値を掘り起こして、伝えていきたいと改めて思いました。
【活動報告】
工房を楽しもう!
■ 6月20日(水)、(参加者4名)
小麦粉から手打ちしてうどんをつくりました。Oさんの持ってきてくださったつゆで、
はたおり探検隊の方々とともにいただきました。
古民家くらし体験(お馬と畑・奥加河荘)
■ 6月6日(木)、7月8日(日) (のべ参加者17名(内子ども7人))
6月は金星の日面通過や雑穀畑の草取り、整体を楽しみました。
岐阜・加子母もりのいえのMさんや岡山からの親子の参加者もあって賑やかでした。
7月は雑穀畑の草取りのあと、お馬に乗りました。
古民家くらし体験(葛川かや葺きの家)
■ 6月21日(木)、 (参加者4名)
夏至のこの日、囲炉裏を囲んでおしゃべりしながら手仕事しました。
13の月の暦が話題にあがりました。
【活動予定】
特に明記しているもの以外は、申し込み不要、参加費無料です。
必要なものはみんなで持ち寄りましょう。
工房を楽しもう!
8、9月はお休みします。
□「工房田んぼ行事」(生活実験工房主催)
■8月18日(土)かかしづくり ■9月29日(土)稲刈り
いずれも10時~12時 屋外展示・生活実験工房にて
□「織姫の会」(近江はたおり探検隊主催)
古民家くらし体験 (お馬と畑・奥加河荘)
馬と鶏、犬猫を一緒に放し飼いにしている大津市大石富川のYさん宅を訪ねて、
雑穀畑や家の作業をしたり、改装した古民家の空間を楽しんだりします。
作業できる服装、お弁当持参です。参加希望の方は中藤まで。
■ 8月8日(水) 10時半-14時半
■ 9月20日(木) (水) 11時-14時半
■ 10月29日(月) 11時-14時半
古民家くらし体験 (葛川かや葺きの家)
移築した古民家「葛川かや葺きの家」(大津市葛川坊村町)で、糸づくりや繕い物、
ヨシ笛・草履などの細工づくりなど、古民家の空間に手仕事を持ち込んで
楽しく作業しましょう。手仕事の道具、お弁当持参です。
(今年は二十四節気を意識した日程に開催します。)
■ 9月6日(木)(「百露」の前日) 10時半-15時
おうみ昔くらし探検塾
滋賀県の昔ながらの衣食住から学び、これからのくらしに活かしていくきっかけの場として、
年間6回、参加者同士で学びあいます。
はしかけ「近江昔くらし倶楽部」の方々はスタッフとして参加ください。(参加される方は事前連絡ください。)
※時間はいずれも10:00-15:00です。
■ 9月8日(土) 綿から着物をつくるくらし 場所:生活実験工房(共催:びわたん)
■ 10月28日(日) イネを育てるくらし 場所:生活実験工房
■ 1月20日(日) 里山体験教室に参加する 場所:野洲市大篠原(共催:里山の会) 参加費:100円(保険料含む)
■ 3月16日(土) 昔のくらしから学びあう 場所:生活実験工房
工房通信2014_8月号(最終号)
工房通信2014.6_7月号
工房通信2014.4_5月号
工房通信2014.2_3月号
工房通信2013.12_2014.1月号
近江昔くらし倶楽部・11月の活動(薪づくりWS・綿にふれてみよう!など)
工房通信2014.6_7月号
工房通信2014.4_5月号
工房通信2014.2_3月号
工房通信2013.12_2014.1月号
近江昔くらし倶楽部・11月の活動(薪づくりWS・綿にふれてみよう!など)
Posted by なかてぃヨーコ at 10:10│Comments(1)
│工房通信・活動予定
この記事へのコメント
リンクされていたので、見つけられました。
吉田には、雪見窓もあったのですよ。
情緒がありますね。
機料品にも、金具の使ってないものを好まれる方がおられます。木製品はしっくりくる、あの金具の音が嫌い等。 私はあのガリッと言わせた綿繰機が好きです。結構、繰れましたよ。まだ使えます。ああやって、機嫌をとりながら、短気を起こさずに、ゆっくりした時が過ごせるのが、その理由です。昔ながらとは、その情緒かも・・・?
吉田には、雪見窓もあったのですよ。
情緒がありますね。
機料品にも、金具の使ってないものを好まれる方がおられます。木製品はしっくりくる、あの金具の音が嫌い等。 私はあのガリッと言わせた綿繰機が好きです。結構、繰れましたよ。まだ使えます。ああやって、機嫌をとりながら、短気を起こさずに、ゆっくりした時が過ごせるのが、その理由です。昔ながらとは、その情緒かも・・・?
Posted by 吉田機料製作所 at 2012年07月19日 12:19