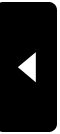2009年07月24日
【 工房通信 】 2009.6.20号
<はしかけ「近江昔くらし倶楽部」を中心とした屋外展示・生活実験工房での活動をご紹介しています。>
琵琶湖博物館、nakatyです。
暑くなったり、肌寒かったり、きつい日差しかと思ったらいきなり豪雨がふったり。
移ろいやすい天候ですね。そんな中でも、身の周りの草木は、黙って緑を茂らせ
生き抜いています。
我が家には自然農法もどきのワイルドな庭があり、毎朝、土に生ゴミをやります。
最近は土に返るのも早く、土にすむ生き物たちのえさやりをしている感じです。
土の上に種をまけば、勝手に芽が出て育つものがあり、食べれるものになれば
ラッキーとありがたくいただきます。
こんな「楽農」ができるのも、日本が近江が土・水に恵まれているおかげ。
こんな身近な財産に気づくことができれば、誰もが無理なく自然体で暮らして
いけるのになあと切に感じます。
滋賀の食事文化研究会さんとの共同企画で小豆の栽培を行います。
11月の「作ってみよう・滋賀の味」でみんなで作った小豆で新米のお赤飯を炊こう!
というのが夢です。7月の中下旬に種をまけば10月下旬から収穫できます。
プランターでも育てられます。やってみたい方には種をお譲りしますので、
中藤までお問い合わせください。
■昔くらし探検・研究会報告
5月9日(土)、愛荘町文化協会主催の講演会『森と湖を結ぶ「菜園家族」』に
参加してきました。
講師は、長年モンゴル遊牧民の研究をされた小貫雅男さん(滋賀県立大学名誉教授)
と伊藤恵子さん(里山研究庵Nomad研究員)。彼らは「菜園家族」のつく著書を何冊も出版して
おられ、現代日本の社会問題を克服する暮らし方として「週休五日制三世代菜園家族」を
提唱しておられます。
講演中、モンゴル遊牧民の暮らしを紹介するドキュメンタリー映像がとても印象的で、
大地に根ざして生きることの大切さ・豊かさを深く感じました。
今後、我々の活動の中で、里山研究庵訪問や、菜園家族の勉強会、映像上映会を
行っていきたいと思います。
【7・8月の活動予定】
■工房を楽しもう!
やりたい人の気持ちと力を合わせ、四季折々の作業を生活実験工房に集って
楽しく行います。
(「工房田んぼの作業・行事」は、工房担当、硲さん(hazama@lbm.go.jp)の担当。)
*7月23日(木)10時~ 工房田んぼ作業・行事(シソジュース、竹細工づくり)
*8月5日(水) 10時~15時半 午前中は工房作業、午後はモンゴル遊牧民のドキュメンタリー映画
「遊牧・四季」(後編)の上映会を行います。<前編は7/25の午後、上映します>
□<衣>近江はたおり研究会:長浜城歴史博物館・協力
*7月7日(火)13時~16時 生活実験工房にて(5月21日の企画が新型インフルエンザで延期)
・話題提供「糸と織りをめぐる湖北・長浜の歴史文化」(長浜城歴史博物館 橋本章さん)
2010年1・2月に開催される特別展「糸の世紀・織りの時代」に関連する内容です。
・活動紹介&交流会:県内各地の織物業に関わる方々にも活動紹介していただきます。
お茶を飲みながら交流し、これからの夢を語り合いましょう。
□<食>作ってみよう・滋賀の味(第3回):滋賀の食事文化研究会・協力
材料をみんなで持ち寄り、近江の旬のわかちあいを楽しみましょう。
あるものを無理なく無駄なく使い切る・生ゴミは土に返す。「立つ鳥あとをにござす」を心して!
*7月25日(土)10時~15時 生活実験工房にて
工房畑で収穫するシソでシソジュースをつくります。主食は持ち寄りのそうめん。
市販のめんつゆと、きちんと調理したつけ汁の違いを味比べします。
持ち寄りの夏野菜をたっぷりいただきましょう。彩りよく、トマトのレモン漬け、カボチャ、きゅうりの
寒天寄せを作る予定です。
午後は、モンゴル遊牧民のドキュメンタリー「四季・遊牧」(前編)の上映会を行います。
<持ち物>・エプロン・三角巾・マイお箸・食器・そうめん・手に入る食材
(ビニール袋などは博物館にはありませんので、袋や風呂敷など必要に応じて準備ください)
□<住>住まいの小学校(第2回):木考塾との共同例会
*8月30日(日)13時半~16時半 生活実験工房にて
テーマは「住まいの今から暮らしを考える」。工房に関心のある方が集い、発表者自身の
家づくりや住まい方について話題提供いただき、「資源が循環するこれからの住まいと暮らし」に
向けて情報共有し、自由に意見交換します。
(住まいの小学校HP http://sumainosyogakkou.shiga-saku.net/)
■「相楽木綿伝承館」オープンと関連イベント
京都府山城郷土資料館を拠点に地元の織物を復元・伝承する活動をしてきた
「相楽木綿の会」が、7月12日、私のしごと館内に伝承館を開設することになったそうです。
□記念講演会
*7月12日(日)14:00~15:30 「相楽木綿をめぐって」
講師 奥村萬亀子氏(京都府立大学名誉教授)
□一日織物講座(講演と体験)
*7月20日(祝)13:00~15:30 「織物のなりたち」
講師 植村和代氏(帝塚山大学教授)
□会場:相楽木綿伝承館(私のしごと館内 tel.0774-98-4510)
京都府相楽郡精華町精華台7-5-1 開館時間 9:30~17:00、休館日 土曜日
■お蔵探検
*8月? 彦根市石寺へのお蔵探検(詳細未定)
県立大学の鵜飼修先生と一緒に行きます。参加希望の方はお問い合わせください。
■湖北学講座「湖国をめぐる織りの文化史」(長浜城歴史博物館)
*8月29日(土)13時半~、長浜城歴史博物館・研修室にて
「湖国に残る織物から学び伝えよう-近江はたおり探検隊-」と題して、
講演と糸紡ぎのワークショップを行います。ぜひ、ご参加・ご協力ください。
これは連続講座の第1回目で、浜ちりめんや養蚕業、近江上布などの講演が続き、
1.2月には同館 で特別展「糸の世紀・織りの時代」が開催されます。
琵琶湖博物館、nakatyです。
暑くなったり、肌寒かったり、きつい日差しかと思ったらいきなり豪雨がふったり。
移ろいやすい天候ですね。そんな中でも、身の周りの草木は、黙って緑を茂らせ
生き抜いています。
我が家には自然農法もどきのワイルドな庭があり、毎朝、土に生ゴミをやります。
最近は土に返るのも早く、土にすむ生き物たちのえさやりをしている感じです。
土の上に種をまけば、勝手に芽が出て育つものがあり、食べれるものになれば
ラッキーとありがたくいただきます。
こんな「楽農」ができるのも、日本が近江が土・水に恵まれているおかげ。
こんな身近な財産に気づくことができれば、誰もが無理なく自然体で暮らして
いけるのになあと切に感じます。
滋賀の食事文化研究会さんとの共同企画で小豆の栽培を行います。
11月の「作ってみよう・滋賀の味」でみんなで作った小豆で新米のお赤飯を炊こう!
というのが夢です。7月の中下旬に種をまけば10月下旬から収穫できます。
プランターでも育てられます。やってみたい方には種をお譲りしますので、
中藤までお問い合わせください。
■昔くらし探検・研究会報告
5月9日(土)、愛荘町文化協会主催の講演会『森と湖を結ぶ「菜園家族」』に
参加してきました。
講師は、長年モンゴル遊牧民の研究をされた小貫雅男さん(滋賀県立大学名誉教授)
と伊藤恵子さん(里山研究庵Nomad研究員)。彼らは「菜園家族」のつく著書を何冊も出版して
おられ、現代日本の社会問題を克服する暮らし方として「週休五日制三世代菜園家族」を
提唱しておられます。
講演中、モンゴル遊牧民の暮らしを紹介するドキュメンタリー映像がとても印象的で、
大地に根ざして生きることの大切さ・豊かさを深く感じました。
今後、我々の活動の中で、里山研究庵訪問や、菜園家族の勉強会、映像上映会を
行っていきたいと思います。
【7・8月の活動予定】
■工房を楽しもう!
やりたい人の気持ちと力を合わせ、四季折々の作業を生活実験工房に集って
楽しく行います。
(「工房田んぼの作業・行事」は、工房担当、硲さん(hazama@lbm.go.jp)の担当。)
*7月23日(木)10時~ 工房田んぼ作業・行事(シソジュース、竹細工づくり)
*8月5日(水) 10時~15時半 午前中は工房作業、午後はモンゴル遊牧民のドキュメンタリー映画
「遊牧・四季」(後編)の上映会を行います。<前編は7/25の午後、上映します>
□<衣>近江はたおり研究会:長浜城歴史博物館・協力
*7月7日(火)13時~16時 生活実験工房にて(5月21日の企画が新型インフルエンザで延期)
・話題提供「糸と織りをめぐる湖北・長浜の歴史文化」(長浜城歴史博物館 橋本章さん)
2010年1・2月に開催される特別展「糸の世紀・織りの時代」に関連する内容です。
・活動紹介&交流会:県内各地の織物業に関わる方々にも活動紹介していただきます。
お茶を飲みながら交流し、これからの夢を語り合いましょう。
□<食>作ってみよう・滋賀の味(第3回):滋賀の食事文化研究会・協力
材料をみんなで持ち寄り、近江の旬のわかちあいを楽しみましょう。
あるものを無理なく無駄なく使い切る・生ゴミは土に返す。「立つ鳥あとをにござす」を心して!
*7月25日(土)10時~15時 生活実験工房にて
工房畑で収穫するシソでシソジュースをつくります。主食は持ち寄りのそうめん。
市販のめんつゆと、きちんと調理したつけ汁の違いを味比べします。
持ち寄りの夏野菜をたっぷりいただきましょう。彩りよく、トマトのレモン漬け、カボチャ、きゅうりの
寒天寄せを作る予定です。
午後は、モンゴル遊牧民のドキュメンタリー「四季・遊牧」(前編)の上映会を行います。
<持ち物>・エプロン・三角巾・マイお箸・食器・そうめん・手に入る食材
(ビニール袋などは博物館にはありませんので、袋や風呂敷など必要に応じて準備ください)
□<住>住まいの小学校(第2回):木考塾との共同例会
*8月30日(日)13時半~16時半 生活実験工房にて
テーマは「住まいの今から暮らしを考える」。工房に関心のある方が集い、発表者自身の
家づくりや住まい方について話題提供いただき、「資源が循環するこれからの住まいと暮らし」に
向けて情報共有し、自由に意見交換します。
(住まいの小学校HP http://sumainosyogakkou.shiga-saku.net/)
■「相楽木綿伝承館」オープンと関連イベント
京都府山城郷土資料館を拠点に地元の織物を復元・伝承する活動をしてきた
「相楽木綿の会」が、7月12日、私のしごと館内に伝承館を開設することになったそうです。
□記念講演会
*7月12日(日)14:00~15:30 「相楽木綿をめぐって」
講師 奥村萬亀子氏(京都府立大学名誉教授)
□一日織物講座(講演と体験)
*7月20日(祝)13:00~15:30 「織物のなりたち」
講師 植村和代氏(帝塚山大学教授)
□会場:相楽木綿伝承館(私のしごと館内 tel.0774-98-4510)
京都府相楽郡精華町精華台7-5-1 開館時間 9:30~17:00、休館日 土曜日
■お蔵探検
*8月? 彦根市石寺へのお蔵探検(詳細未定)
県立大学の鵜飼修先生と一緒に行きます。参加希望の方はお問い合わせください。
■湖北学講座「湖国をめぐる織りの文化史」(長浜城歴史博物館)
*8月29日(土)13時半~、長浜城歴史博物館・研修室にて
「湖国に残る織物から学び伝えよう-近江はたおり探検隊-」と題して、
講演と糸紡ぎのワークショップを行います。ぜひ、ご参加・ご協力ください。
これは連続講座の第1回目で、浜ちりめんや養蚕業、近江上布などの講演が続き、
1.2月には同館 で特別展「糸の世紀・織りの時代」が開催されます。
工房通信2014_8月号(最終号)
工房通信2014.6_7月号
工房通信2014.4_5月号
工房通信2014.2_3月号
工房通信2013.12_2014.1月号
近江昔くらし倶楽部・11月の活動(薪づくりWS・綿にふれてみよう!など)
工房通信2014.6_7月号
工房通信2014.4_5月号
工房通信2014.2_3月号
工房通信2013.12_2014.1月号
近江昔くらし倶楽部・11月の活動(薪づくりWS・綿にふれてみよう!など)
Posted by なかてぃヨーコ at 09:31│Comments(0)
│工房通信・活動予定