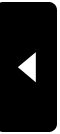2015年03月05日
草津市の小屋の解体、ミラクルな最終報告!
草津市の解体される小屋のこと、
たくさんの方々のお心とお力を頂き、ありがとうございました!
今回は、自分で仕掛けてどうにかしようとは、敢えてせず、
ご縁あるみなさんから寄せられたお心とお力をつなぐことだけしよう
と決めていました。
正直なところ、ここまでの展開・結果が得られたことに驚いています。
2/20から始まった解体工事の間も、ミラクルの連続でした。
× × ×
2/20、足場を組んでいる横で、夏障子を取りに来られた方と作業し終えて、
「これで、もう現場には行かないでおこう」と思ったのですが、
末娘に「河原におうちを建てるための材料がほしい」と乞われて、
2/24、現場に行ったのです。
すると、解体作業をしている様子がない。お休み?
建物の一間庇はなくなってたけど、躯体はそのまま、二階の床板もあり。
・・・これは、床板、はがせるぞ!と思い、
現場監督さんに電話して許可を得てから、
コーナンプロで、バールとハンマーをゲットして、床板はがし開始!
そこへ、ヘルメットをかぶった作業員の方がひとり、来られたのです。
これから少し解体作業をするとのことでしたが、
まだ、始めないとのことだったので、急いで床板はがしに取り掛かりました。
半分くらいはがしたところで、作業員さんが二階に上がってこられました。
まだ、大丈夫とのことだったので、床板はがしに精を出しながら、
世間話をしていたら、
なんと、このベテランの作業員さん、
十数年前、守山市の鍛冶屋さんの古い建物の解体のときに、
「この建物は壊してほしくない」と言い張っていた私と
どうも出会っていたようなのです。
(さらに、今回の現場監督さんも同じ現場で作業していたとのこと)
#鍛冶屋さんって、大事なんですよ。
昔の農具を使うくらしを続けようと思ったら、絶対に必要になる仕事。
守山市では残せなかったけど、
新旭の鍛冶屋の建物は家主さんを説得してまだ残っています。
長浜の鍛冶屋という集落では、作業場を修復して、鍛冶仕事をやっておられます。
今回の小屋見学にも、若い野鍛冶さんが来られたんですよ!
十数年ぶりの解体現場での再会。こんなことって、あるでしょうか?
× × ×
そのあとも、ミラクルは続きます。
はがした床板を、欲しいと言っていた改築中の方のところへ届けたら、
女の大工さんが待っていてくださいました。
その大工さん、土壁がほしいけど、目下資材置き場を探し中。
取り置けるなら、ぜひ欲しいとのこと。
すると、翌日、解体現場の敷地内の空き地に、
土壁を残しておくのに丁度いい場所を見つけてしまったのです。
そこで、家主のご主人に電話で相談したら、
「もう、小野さんの好きにしてください。
思い残すことがないように、存分にやってくれはったらいいです。」
と、半ばあきれた笑い口調で、返してくださり、
2/27、大工さんと現地で会って、現場監督さんの許可ももらって、
土壁を空き地に残せることになりました!
× × ×
結局、24日から27日まで、毎日、現場に通いました。
小屋が解体される様子を見るのは、心が痛むのでは・・・と思っていたけど、
それは思い込みでした。
十字梁の短い方を、ユンボのつかみハサミが一掴みして、
すっと、軽やかに外してしまった瞬間を目にしたときは、
「すごいっ」と心おどりました。
屋根に上った作業員さんが、チェンソーで丸太梁を切り、
ユンボのハサミが、それをつかみ取り、屋根が落ちる。
チェンソーで切った桁も、ユンボのハサミでつかんで引っ張ると、
自然に壁も倒れ、丁寧に土と竹と木材を分けたものを、
つかみハサミで優しくつかんでトラックの荷台へ。
太くて長い材もハサミでつかむだけで簡単に折れてしまう、
そんな圧倒的なパワーをもつ一方で、
うすいコンパネや細い材1本も、傷つけずに細やかに扱える、
そんなユンボの扱いには、感動すら覚えました。
そして、それをフォローする男たちの動き、
全てがまさに芸術的で、ずうっ~と、見惚れてしまってました。
「ああ、こんな男たちのおかげで、
この、いまの、世の中が作られたんだなあ」と、
改めて感じ入りました。
× × ×
・・・あ、そうそう、私は末娘のリクエストで、
河原にお家をたてるための材料を集めに来てたんだった
と思い出して、
木材が集められるたびに、「これもらっていいですか」と声をかけて、
適当な大きさの角材・柱、板を運び出してたのですが、
十数年ぶりに再会したベテラン作業員さんに、
「この丸太梁も、私に扱える大きさなら、ぜひほしいのですが」
ともらしたら、
「おい、お前の出番だぞ」と一番若い力持ちの作業員さんに指示して、
1メートルくらいの長さに切ってくれました。
そして、その若い作業員さんがそれを軽々と持ち上げて仮置き場まで
持って行ってくれました。
私は、その1メートルをころころ転がして、よいしょっと立てて、
ばたんと倒す・・・という方法で、運びました。
車の荷台までかつぎあげるのは無理でも、
転がすための緩やかなスロープを丈夫な板か何かで作れば、
車にのせることはできるでしょう。
家主のご主人と、弟さんが、残しておきたいとのこと。
あとは、リクエストされた、木地師さんにお渡ししようと思います。
× × ×
・・・こうして振り返ってみると、
今回の小屋の解体の中で、「これがほしい」とリクエストされ、
その方が諦めなかったものは、
結果的に、すべて手に入れることができた気がします。
(床板も、建具も、丸太梁のかけらも、そして土壁も・・・)
自分の中のちっぽけな世界で思いつくことでどうにかしようとするのでなく、
大きな天・宇宙・世界に委ね、
ご縁あった方々のお心とお力をすべて無駄にすることなく、
最後まで諦めない
ことで、ここまでのことが成ったことに、深く深く感謝いたします。
ありがとうございました!
たくさんの方々のお心とお力を頂き、ありがとうございました!
今回は、自分で仕掛けてどうにかしようとは、敢えてせず、
ご縁あるみなさんから寄せられたお心とお力をつなぐことだけしよう
と決めていました。
正直なところ、ここまでの展開・結果が得られたことに驚いています。
2/20から始まった解体工事の間も、ミラクルの連続でした。
× × ×
2/20、足場を組んでいる横で、夏障子を取りに来られた方と作業し終えて、
「これで、もう現場には行かないでおこう」と思ったのですが、
末娘に「河原におうちを建てるための材料がほしい」と乞われて、
2/24、現場に行ったのです。
すると、解体作業をしている様子がない。お休み?
建物の一間庇はなくなってたけど、躯体はそのまま、二階の床板もあり。
・・・これは、床板、はがせるぞ!と思い、
現場監督さんに電話して許可を得てから、
コーナンプロで、バールとハンマーをゲットして、床板はがし開始!
そこへ、ヘルメットをかぶった作業員の方がひとり、来られたのです。
これから少し解体作業をするとのことでしたが、
まだ、始めないとのことだったので、急いで床板はがしに取り掛かりました。
半分くらいはがしたところで、作業員さんが二階に上がってこられました。
まだ、大丈夫とのことだったので、床板はがしに精を出しながら、
世間話をしていたら、
なんと、このベテランの作業員さん、
十数年前、守山市の鍛冶屋さんの古い建物の解体のときに、
「この建物は壊してほしくない」と言い張っていた私と
どうも出会っていたようなのです。
(さらに、今回の現場監督さんも同じ現場で作業していたとのこと)
#鍛冶屋さんって、大事なんですよ。
昔の農具を使うくらしを続けようと思ったら、絶対に必要になる仕事。
守山市では残せなかったけど、
新旭の鍛冶屋の建物は家主さんを説得してまだ残っています。
長浜の鍛冶屋という集落では、作業場を修復して、鍛冶仕事をやっておられます。
今回の小屋見学にも、若い野鍛冶さんが来られたんですよ!
十数年ぶりの解体現場での再会。こんなことって、あるでしょうか?
× × ×
そのあとも、ミラクルは続きます。
はがした床板を、欲しいと言っていた改築中の方のところへ届けたら、
女の大工さんが待っていてくださいました。
その大工さん、土壁がほしいけど、目下資材置き場を探し中。
取り置けるなら、ぜひ欲しいとのこと。
すると、翌日、解体現場の敷地内の空き地に、
土壁を残しておくのに丁度いい場所を見つけてしまったのです。
そこで、家主のご主人に電話で相談したら、
「もう、小野さんの好きにしてください。
思い残すことがないように、存分にやってくれはったらいいです。」
と、半ばあきれた笑い口調で、返してくださり、
2/27、大工さんと現地で会って、現場監督さんの許可ももらって、
土壁を空き地に残せることになりました!
× × ×
結局、24日から27日まで、毎日、現場に通いました。
小屋が解体される様子を見るのは、心が痛むのでは・・・と思っていたけど、
それは思い込みでした。
十字梁の短い方を、ユンボのつかみハサミが一掴みして、
すっと、軽やかに外してしまった瞬間を目にしたときは、
「すごいっ」と心おどりました。
屋根に上った作業員さんが、チェンソーで丸太梁を切り、
ユンボのハサミが、それをつかみ取り、屋根が落ちる。
チェンソーで切った桁も、ユンボのハサミでつかんで引っ張ると、
自然に壁も倒れ、丁寧に土と竹と木材を分けたものを、
つかみハサミで優しくつかんでトラックの荷台へ。
太くて長い材もハサミでつかむだけで簡単に折れてしまう、
そんな圧倒的なパワーをもつ一方で、
うすいコンパネや細い材1本も、傷つけずに細やかに扱える、
そんなユンボの扱いには、感動すら覚えました。
そして、それをフォローする男たちの動き、
全てがまさに芸術的で、ずうっ~と、見惚れてしまってました。
「ああ、こんな男たちのおかげで、
この、いまの、世の中が作られたんだなあ」と、
改めて感じ入りました。
× × ×
・・・あ、そうそう、私は末娘のリクエストで、
河原にお家をたてるための材料を集めに来てたんだった
と思い出して、
木材が集められるたびに、「これもらっていいですか」と声をかけて、
適当な大きさの角材・柱、板を運び出してたのですが、
十数年ぶりに再会したベテラン作業員さんに、
「この丸太梁も、私に扱える大きさなら、ぜひほしいのですが」
ともらしたら、
「おい、お前の出番だぞ」と一番若い力持ちの作業員さんに指示して、
1メートルくらいの長さに切ってくれました。
そして、その若い作業員さんがそれを軽々と持ち上げて仮置き場まで
持って行ってくれました。
私は、その1メートルをころころ転がして、よいしょっと立てて、
ばたんと倒す・・・という方法で、運びました。
車の荷台までかつぎあげるのは無理でも、
転がすための緩やかなスロープを丈夫な板か何かで作れば、
車にのせることはできるでしょう。
家主のご主人と、弟さんが、残しておきたいとのこと。
あとは、リクエストされた、木地師さんにお渡ししようと思います。
× × ×
・・・こうして振り返ってみると、
今回の小屋の解体の中で、「これがほしい」とリクエストされ、
その方が諦めなかったものは、
結果的に、すべて手に入れることができた気がします。
(床板も、建具も、丸太梁のかけらも、そして土壁も・・・)
自分の中のちっぽけな世界で思いつくことでどうにかしようとするのでなく、
大きな天・宇宙・世界に委ね、
ご縁あった方々のお心とお力をすべて無駄にすることなく、
最後まで諦めない
ことで、ここまでのことが成ったことに、深く深く感謝いたします。
ありがとうございました!
草津市南山田町のお蔵(小屋)のその後の報告
facebook小野容子、2015.3.16 10:25の投稿
新聞掲載「昔の道具博物館」、そのうらばなし
2/19 草津市の小屋見学、「昔の道具博物館」作り・参観のご案内
2/12、2/13、2/14、草津市のお蔵見学・民具活用のご案内
2/4、2/5、2/7、2/9、草津市のお蔵見学・民具活用のご案内
facebook小野容子、2015.3.16 10:25の投稿
新聞掲載「昔の道具博物館」、そのうらばなし
2/19 草津市の小屋見学、「昔の道具博物館」作り・参観のご案内
2/12、2/13、2/14、草津市のお蔵見学・民具活用のご案内
2/4、2/5、2/7、2/9、草津市のお蔵見学・民具活用のご案内
Posted by なかてぃヨーコ at 20:03│Comments(0)
│草津市のお蔵(小屋)2015